 目次へ
目次へ
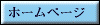
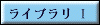
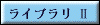
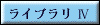
食のエッセイ>シベリアの森よ、お前もか 1992/11/ 6
NHKプライム10「崩れゆく永久凍土」、この映像を僕達は、いや日本人は どう受け止めればよいのだろうか。 アマゾンの森林伐採、東南アジアのマングローブ伐採、そして今、シベリアの 大地から森林の悲鳴が聞こえてくる。 臨時国会の冒頭、日本の首相は「景気低迷の中、住宅需要に明るさが見える」 との所信表明演説を行った。 政治疑惑や灰色の金にまつわる話題、そして景気低迷、国民的関心は浮き世の 痴話や政治パフォーマンスにばかり集まってしまうが、不平不満を言いながら もカウチポテトでにわか評論家になれる足元が見えていない。 「地球温暖化なんていったって、環境保護論者が神経質に騒いでいるだけじゃ ないか」、それよりも浮き世の政治と金のゴシップを見ている、いや、見せて いる方がトレンディらしい。 僕は、森林破壊、そして地球環境のとどめがタイガ伐採で訪れるのではないか と思った。 ソ連邦の解体は経済的破綻が根底にあるとされるが、経済開放によって目先の 外貨稼ぎに消滅していくシベリアタイガ、弱みにつけこんでせっせと木材の大 量買い付けに奔走する日本資本。 シベリアの森林伐採従事者たちのサラリーは、6,000円だという。 この所得を週休2日制や労働時間短縮を求めながら自国のGNPにひたすら貢 献し、経済不況を叫ぶ人達はどう見るだろうか。 彼らは、この6,000円の所得を得るためにひたすら木を切り倒さねばなら ないノルマを達成せねばならないのだ。 その6割、それも大径木が日本という一国に向けて輸出されていく。 買い付け契約によってシベリアにもたらされるものは外貨ではなく、伐採運搬 に要する車両提供なのだという。 日本企業は、国内的には環境キャンペーンや企業メセナをとり繕うが、アマゾ ン、東南アジアで非難されてきた愚行のとどめをシベリアタイガの森林伐採で さそうとしている。 金権汚職や経済不況、確かに腹立たしいことはあるだろうが、それは物質文明 の華やかさと天然資源、エネルギー大量消費を前提とした暮らしの中で浮き世 の常に踊っている、踊らされているだけではないか。 「生活大国」、年収の5倍で持ち家が買える政治と時の首相はおっしゃってい るが、人間的関係がますます希薄に、そして核家族化が出生数の減少という金 満の嘆きに至って、2世代住宅を乱立させて生活大国づらしたい土壌には救い ようのない愚かさを感じる。 豊かな生活環境のあった農村をうちのめし、都市という狭い住空間に労働力を 囲いこみ、狭いが故に持ち家の夢をあおる、うちのめされたのは農村ばかりで はなく、家族形態でもあったことに目覚めるべきではなかろうか。 シベリアで切り倒された大径木は、厳しい自然がもたらす緻密さゆえにシロア リにも強い住宅用の柱として日本の商社が買い付けていく。 シベリアの地表数メートル下に数万の眠りについていた永久凍土が、タイガの 伐採によってどんどんと氷解している。 パソコン通信によっても、マーシア、サラワクでの森林伐採によって原住民の 生活が脅かされている報がいちはやく世界を駆け巡った。 熱帯の土壌は貧栄養なので、一度樹木が伐採されてしまうと痩せた土壌がむき 出しとなってしまい、あとは熱帯特有の降雨が大地を果てしなく侵食する。 ここにも、経済的貧困が天然資源の切り売りに走らねばならない第三世界の窮 状につけこんだ「経済大国」のもっともらしい理屈があった。 その経済的正当性が外貨を求める国の森林を破壊し、エビの養殖池が伐採の追 い撃ちをかけている。 国際的批判を浴びる頃には、遅まきながら「国家的支援」の名のもとに森林復 元のためのプロジェクトがNGO活動の後を追って始められる。 今度は、シベリアである。 連邦解体、経済体制の転換に迫られた弱みにつけいる点で、経済的優位のおご りとそうした状況をつくり出す術をどうやら東洋の離れ小島の企業家たちは持っ ているらしい。 悲劇的なのは、そうしたおごりをおごりと感じないで暮らしている勤労者たち、 生活者たちであり、高度に分業化された経済システムにおいては元締めの暗躍 と環境破壊の罪は広く、浅く国民の間に分散されてしまう。 永久凍土が解けることの意味は、単にシベリアの皆伐後に沼が出現するという ことに留まらない。 もちろん、寒冷な気候と降水量が少ない過酷な生命環境下で、地表数メートル の土壌と浅い樹木の根がその生態系の働きで絶妙のバランスで保ってきた凍土 との水のやり取りを絶たれてしまうわけだ。 太陽光は容赦なく凍土を解かし始め、地表にしみだし、伐採後に沼が出現する。 最初は小さな沼も、地表下の永久凍土の氷解というドミノ倒しによってどんど と大きくなっていき、周囲の樹木をも飲み込んでいく。 やがて降水量に乏しい気候が沼を干上がらせ、大量の塩分が地表に析出し、植 物もはえない不毛の大地を生み出す、そして寒冷地砂漠がタイガにとって変わ る。 ここまでは、日本からみれば他所の国の出来事かもしれない。 しかしながら、いままで測定されたことのなかったシベリアの森林の二酸化炭 素の吸収量が熱帯雨林のそれをしのぐ事実が明らかとなってきた。 エネルギーの大量消費の結果、つまり経済先進諸国の物質的栄華によって吐き 出された二酸化炭素を浄化するしくみが、生活大国に浮かれるそれらの国によっ て壊されているのだ。 とりわけ、木材資源を世界でもっとも消費する日本の責任は重い。 日本との商社との契約を履行するために課せられた伐採ノルマは、容赦なくシ ベリアの大地をトラクターで踏み荒らさせ、幼木をも踏みにじっていく。 大木といっても、凍土の上のわずかに表土に根を張った森林、残された若木も 根をやられて、やがては枯れていくものがほとんどという。 この夏、初めて行われた日本とロシアの合同気象観測の結果、恐るべき事実が 明らかとなった。 伐採後に出現した沼から大量のメタンが発生していたのだ。 メタンは、二酸化炭素よりもはるかに地球の温室効果の高いガスである。 その発生源は、沼の中で朽ちた樹木の残骸ばかりではなかった。 氷河期が何万もかかって永久凍土の氷の中に閉じこめた高濃度のメタンの気泡、 この気泡が眠りを覚ましたのだ、まさに開けてはならぬパンドラの箱に消費文 明は手をつけてしまった。。 世界的異常気象、オゾンホールの出現、そして大気汚染に酸性雨。 一国の生活大国化が、いったいどれほどの地球的犠牲のもとに成り立っている のか、誰かが何とかといった無責任な、他人ごとのような状況認識では自分で 自分の首をしめているようなものだ。 異常気象は、現に世界のあちこちで多発している、これは事実なのである。 アメリカがコメの市場開放を迫る理由に、今までアメリカの輸出穀物を支えて きた小麦、トウモロコシが干ばつなどの異常気象の影響を受けやすく、あまり 気象の影響に左右されないイネに戦略作物をシフトさせようとしている、とい 説がある。 気象異常によってもっとも影響を受けるのは、食糧生産なのだ。 その食糧をほとんど海外に依存しようとしている生活大国、まさに砂上の楼閣 ではなかろうか。 都市と農村のバランスの見直しやグリーンツーリズムも結構、しかし、足元を 見ないで目先の満足に目を奪われてしまっては、使えもしない金に埋もれて滅 びを待つ栄養を絶たれた水耕栽培の野菜民族になってしまうだろう。 それほどシベリアのタイガの消滅の意味は大きく、深刻であり、切実な問題と して受け止めねばならない事実ではなかろうか。 政治家がスキャンダルで辞めることよりも、シベリアの森の現実の方が心配だ。 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
子供たちのアゴの形が、ずいぶんときゃしゃになったことにお気付きの諸兄 に拙文をぜひともお贈りしたい。 美形でならす今日のアイドルタレントたちから何を学ぶことができるのか、こ の考察はなかなか奥深いものがある。 世の美形の判断が何によって支えられているのかは興味の尽きないところだが、 細面のうりざね顔、出てくる若年タレントたちの多くは実にスマートなアゴを 持っている。 たぶん、このアゴのかたちがきしゃになったことを嘆きまくるのは、まず歯医 者さんたちであるに違いない。 人間の進化が、脳の容積によって、特に新皮質の発達によって特徴づけられる ように、組織機能とは「使えば発達する」。 このことは、逆に「使わなければ退化する」ことも意味する。 アゴが逆三角形にとがりはじめたことは、いってみれば「噛まずにすむ食生活」 がアゴの骨の成長にブレーキをかけていることの証しでもある。 家畜とともに暮らしていると、家畜の哀れを思うこともあれば、時にうらやま しくも感じることもある。 特に牛やヒツジなどの反芻動物たちが、のんびりと噛み返しをやっているのど かな情景には、嫉妬に似た気持ちがわきあがるのだ。 進化論的に言ってしまえば、肉食獣の餌となる弱い草食獣が食餌の機会を有効 に活用するために発達させてきた胃のしくみが反芻なのかもしれない。 この反芻、考えれば考えるほどよくできたしくみであることに驚く。 我々単胃動物は、胃液を分泌する腺胃しかもっていないわけだが、噛み返しを 行う草食動物には基本的に肉食をしなくても生きていける複数の胃袋があたわっ ている。 プロトゾアと呼ばれる微生物たちが、「あるじ」によって噛み返された草を餌 に胃の中で増殖し、それら微生物たちが分解する炭水化物、そして微生物が作 り出す脂質、蛋白質、ビタミン前駆物質によって「あるじ」が生きていくとい う見事なまでの共生のしくみ。 肉食獣に追いかけられて、おちおち草を食べていることができないという必要 が生み出した消化のしくみなのだろうが、その反芻を支える頑強なアゴを家畜 に見るたびに、ファーストフードを片手に受験勉強に追いまくられ、芸能タレ ントにつかのまの安息を見出す子供たちのアゴが不敏に思えてくるのだ。 家畜、特に牛が本来の姿として草をはみ、それを反芻させて健康を保つとい うこと、これは家畜であろうがなかろうが最低限確保されねばならない生存の ための条件なのである。 酪農の世界では、粗飼料の大切さはとても重要とされている。 「粗飼料」の対局には「濃厚飼料」があるわけだが、「粗」からくるイメージ ゆえにその大切さをうとんじる向きがある。 確かに、濃厚飼料は栄養的にみれば「濃厚」なのかもしれないが、草を噛み返 すという運動的な生理を奪うばかりか、噛み返された草を餌として待っている 反芻胃の中の微生物たちの活動にも大きな影響を与えてしまう。 これは、栄養のつまったカプセルを飲み込むだけの食事みたいなもので、体内 の生理機能などおかまいなしの燃料補給マシン扱いなのだ。 では、なぜ濃厚飼料が必要となり、またなくてはならないものになってしまっ たのか。 結論から言ってしまえば、人間の経済的エゴイズム、これに尽きる。 サシの入った松阪牛の牛肉が食べたい、こくのあるうまい牛乳が飲みたい、そ れを育てる農民は、もっと収入が欲しい。。 工業製品との生産性産業間比較に明け暮れる現代では、家畜が機械扱いされて しまうようになるのである。 より早く太る、より多く乳を出す、そのためには経済的にペイすればあらゆる 手段が講じられる。 成長ホルモンが皮下に埋めこまれたり、より多く乳を出させるために濃厚飼料 が多給されたり。。 目的のためには、とことん効率を追求してやまない人間社会である、哀れ牛さ んたちは草の噛み返しからどんどんと遠ざけられてしまう。 哀れなのは家畜ばかりと思いきや、美麗な顔立ちを肴に浮き世の飽食に明け 暮れる現代人は輪をかけて哀れむべき存在ではないか。 なにせ、あまり噛む必要のない食品が次から次へと登場してくる。 と同時に、これがまた調理いらずといった親切丁寧なしろものときた日には、 ますます調理器具離れが加速していく。 コンビニエンスストアに群がる手合いは、実に巧みにファーストフーズを活用 する名人といっていい。 しかしながら、噛み返しをしている牛さんたちにある種、うらやましさを覚え る小生にとっては、噛み返す必要を奪いさるこうしたおせっかい食品のオンパ レードは不快以外のなにものでもない。 食品添加物だらけの調理済み食品が食い物としてのあるべき姿、すなわち健康 で、食べることに喜びを与えることを満たしているとは到底思えないし、あた かも何者かの都合によって与えられた餌をついばむ家畜同然の構図が見え隠れ して、エコノミックアニマルの語意が実にシリアスに迫ってくる。 経済先進国を自ら語る諸氏も、飽食の行き着く先を餌とした「エコノミックア ニマル」という家畜であった、なんてこれではあまりに芸のない話ではないか。 牛の噛み返しに学ぼう。 噛むことによって、唾液の分泌がうながされることはもちろん、アゴの骨を十 分に発達させ、より咀嚼に適した体を自らつくりだすことになる。 噛み返すという動作は、その食べ物が本来もっている味わいを引き出すための 重要なプロセスなのである。 現代食は、味付けでごまかしたイミテーションみたいなコピー食品の洪水であ るのだから、口にした瞬間の味覚騙しが命ともいえる。 だから、長々と噛み返されたのでは外張りのメッキがはがれてしまい、エコノ ミックアニマルが成長しない。 そのために、生まれ落ちたときからせっせと噛まずに済む餌を与え続けられて いるのかもしれない。 「噛み返す、咀嚼する」という言葉は、内容を噛み砕く、吟味するという含蓄 のある響きも持っている。 現代人に欠乏しているのは、矢のごとく飛び交う事象を再び噛み返して消化す る時間のようにも思える。 絶えず何かに追われているような切迫感、それでいて、最先端という響きにふ らふらとなびいていく性。 ファーストフーズに群がる人間たちは、「最先端」という檻に閉じこめられた 哀れな家畜じゃないだろうか。 時代の流れを噛み返し、反芻をくり返し、そして自分にとって、社会にとっ て欠乏しているものは何なのかをじっくりと考える、そして対処していくこと のできる頑強な「アゴ」を持ちたいものである。 もちろん、軟弱なコピー食品に騙されて、食べ物が本来兼ね備えていなければ ならない健康を保証する役割、風土に根差した地方色のある味わい、それを口 にする喜びを見失っては何にもならない。 「噛み返す」という意味が、実は現代人の心と体、労働の本質、生命集合体と しての地球につながっていくような気がするのである。 「最先端」は麻薬のようなもの、薬にもなれば廃人をも生み出す。 麻薬中毒患者の実態を他人ごとのように見ている自分が、実は人類が進化の過 程でつくりだした最強の麻薬「最先端」の中毒患者そのものなのかもしれない。 薬と麻薬のさじ加減を見失わないための「自覚」を諭すものこそ、草原で自然 の摂理とともに生きる野生動植物たちが教える「噛み返し」ではないだろうか。 頑強な「アゴ」でバリバリとセロリを噛み砕いていく爽快さ、虚飾を振り払っ て英知をまっとうできる人間、社会に生きたいものでる。 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
十勝の農民たちは、ここしばらく、小豆の相場を固唾を飲んで見守っている。 小豆の作付けは、主産地十勝においては1万4千haを前後して、ほぼ安定して作 られている農作物であるが、労力や生産性といった問題から豆類の敬遠基調の 例外ではない。 ただ、輪作を構成する大切な作物であることに変わりはなく、連作、過作によっ て収量が著しく減少する正直な作物でもある。 ある年には、1俵60kgあたり1万2〜3千円という安値があるかと思えば、国産も のが品薄基調だと現地価格で4万円を越えたりもする。 政府の減反政策による転作奨励作目であるのだが、ここにきての減反緩和の動 きが転作地帯での小豆作付けを見直しさせる結果となり、産地市況は久しぶり の高値で推移している。 普通、小豆の収穫量は10a当たり3俵から4俵が普通だから、仮に4万円の価格だ と反(10a)当たり12万円以上の水揚げとなる。 十勝のような粗放的畑作農業生産地帯にあっては、10aあたり10万円を越える 農業所得確保が当面の努力目標とされているので、安定的にこの価格が続いて いれば豆作もそう敬遠される農作物ではなくなるかもしれない。 しかし、現実はそうやさしくはない。 小豆需要は、そのほとんどが和菓子用の餡向けに消費されているので、高値の 小豆は和菓子屋さんを直撃する。 大阪の知り合いの和菓子屋さんから、「今年の小豆の出来はどうですか」と、 心配そうな声で電話をもらった。 和菓子屋さんの仕入れ値が、一枚(30kg袋)5万円を越えているという。 例年だと、一枚2万5千円くらいだというから、倍の価格となっているらしい。 和菓子の見直しブームもあるが、餡の原料価格が倍になったからといって、製 品の和菓子の価格を倍にすることもままならず、産地と消費地のシーソーには 複雑な思いがする。 ただ、輸入物の安価な小豆では、和菓子にした時の風味に大きな差があるとい う。 セントラルキッチンシステムを持つ大口実需者たちは、安価な輸入物に走ると もいわれている。 他の農作物が価格低迷にあえいでいる中、小豆価格の高値は生産者にとっては 福音ではあるのだが、実需者の声を聞くと素直に喜んでいられなくなる。 それにつけても、現地で60kg4万円の相場(今日は、3万7千円くらいだそうだが) の小豆が、どこでどう巡りめぐって30kg5万円の小豆に化けてしまうのだろうか。 このからくりが、生産者当人にとっては実に不可解だし、実需者たる和菓子屋 さんたちにとっても謎なのである。 輸送経費といっても、国鉄5トンコンテナで関西まで送るとすると、およそ80 俵の小豆を詰めることができるのだが、その経費は8万円だという。 60kg換算では、1,000円ではないか。 生産者価格と、実儒者価格の格差を考えると、仮に輸送経費を差し引いてもと んでもない中間マージンが存在することになる。 中小の和菓子屋さんたちが、個々に一回あたり80俵(160枚)の原料小豆を扱 えるかどうかも問題だが、仮に何軒かのお店が集まって、この5トンコンテナ を有効に利用できなら、こんな異常な事態もなんとかなるのではと思ってしま う。 また生産地でも、毎日相場に釘付けになっては、不安定な価格に一喜一憂する 農民たち、先の見えない小豆、作付け意欲も安定生産もあったものではない。 豆の消費、自分が豆を作っているから言うわけではないが、食物繊維や微量 ミネラルの補給という意味からも、もっともっと生活の中に増えていって欲し い食材なのだ。 単に和菓子の原料としか思われていない現実もさみしいばかりだが、食事の洋 風化、外食化が進行するなかで、栄養のバランスの偏りがもたらす悲劇も指摘 されてきている。 豆を作っている立場から言うと、その出来は天候には大きく左右され、しかも 最も手間がかかる(機械化が遅れていて、肉体労働を要する)作物の一つなの だ。 腰をかがめ、自然乾燥させるための手間をかける、この十勝という地方がもつ 気象条件と地味が豆に独特の風味を与えているといってもいい。 ところが、豆の相場にそんな手間暇などはいっこう考慮されることなどない。 高度経済成長と今日の産業を下支えしてきた下請け生産部門が、大口発注主で ある親会社の意のままに安価生産を強いられているのと状況は似ている。 もちろん、高い農産物を声高に叫ぶつもりはないのだが、ものの価値をそれを 手掛ける人の手間と気持ちも含めて見ていただきいということなのだ。 ものを作っている立場として、原料として十勝産小豆を使ってくださっている 和菓子屋さんたちが、それぞれ製品としての和菓子に託す気持ちもわかる。 その和菓子を口にする人たちが、職人さんたちの気持ちのいくばくかでも感じ てくださればいいのだが、はてさて、実際はいかがなものだろうか。 生産と消費の結び付きが希薄になってきて、とくかく作るだけ、儲けるだけの 関係が蔓延してしまえば、一番の被害を被るのは最終消費者たる自分たちなの だということをしっかと押さえねばならないのではなかろうか。 僕だって、自分の作った豆を使ってくださる方の存在を知れば、その期待に少 しでも応えるための次の生産意欲が起きるのだから。 そして、あまりに不可解な現地価格、実需者価格に対し、双方が納得できる情 報交流の関係を自らが作り、解決していかなくてはいけないと思うのだ。 そうした関係から作られた和菓子を口にすることができた消費者、是非ともお 味の感想をお返しいただきたいものである。 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
久しぶりに、NHK特集=緊急リポート「世界の中の日本 食糧−国家の選択」 1988 日本放送出版協会 をひっぱりだして、読み返してみた。 同名のNHKの特集番組を取材リポートを交えて紙上に再録したものである。 当時は、ガット交渉の舞台にアメリカが「コメ」を持ち出した時期でもあり、 日米貿易摩擦解消問題も手伝って、日本の農業生産の在り方が議論されていた 時期でもあった。 それから4年、農産物の関税化による市場開放の動きは、各国の思惑、利害が 複雑に交錯しながも、アメリカとECの基本合意成立から、一気にガット交渉 妥結に向かって動き始めた。 このままでは、日本だけがゴネてウルグアイラウンドを壊すことはできないと いうなしくずし的結末を迎えるシナリオがますます真実味を帯びてくる。 コメの市場開放は飲めないという国会決議をしながらも、ここにきて宮沢首相 が政治的決断の時期を言い出すのは、「コメ市場の関税化による開放やむなし」 を首相自らがほのめかしたということでもある。 スキャンダラスな話題に事欠かない金権体質まる抱えの政権与党が、はたして この国家的選択に対し説得力をもった申し開きができものかどうか、司法にも 期待が持てない現実では、少しでも早く選挙をとも言いたくなる。 4年前の公開討論の再録を読み返していて、ふとひらめきを覚えるフレーズに 行き当たった。 「日本の農業はこれから何を守り、何を捨てるのか」 「農業もスクラップする勇気を」 なるほど。。 農業や食糧問題において、財界と農業団体、消費者と生産者の意見の食い違い の大元は、ひょっとするとここにあるんじゃないだろうか。 農業も産業の一つ、競争原理が働かねば進歩はありえないし、切磋琢磨の中か ら市場で生き残れる力を得ることができる、農業も例外ではない。。 だから、貿易自由化にも耐えられる競争力を持て、関税化を受け入れろという わけだ。 「農業と工業は違う、同じ土俵で相撲はとれない」、「いやいや、国際貿易の 中で日本が存在している限り、例外などありえない」。 「農業にだけ、特別な補助金を出していること自体、不公平ではないか」 「農業は、先進国どこでも保護されている、農業補助はありたまえ」 公開討論などをやると、議論のすれ違いはいつも同じだ。 そこで、先程のフレーズ、「何を守り、何を捨てるのか」なのだ。 農業とは、もともと「捨てる」ということになじまない営みなのではないか。 工業社会とは、寿命が尽きるという生産物をいかに数多く売り込むか、つまり 需要を絶えず作り出しながら成立している社会といえるだろう。 そこには、どの社の製品が支持されるかという競争もあるけれど、一面、作っ たものがやがてはゴミとして捨てられていくという仕掛けもあるわけだ。 この「捨てる」ことをいとわない風潮が、いったいどれだけ脳天期で世間知ら ずな社会を作り出していることか。 資源物理学でお馴染みの槌田敦さんは、エントロピーのことを汚染の量と説明 し、何かが変化したり、何かが活動すれば生ずるものがエントロピーであり、 これは不可避的に汚染の量が増えることとおっしゃっている。 以下、「捨てる」ことの科学を槌田さんの著作から紹介する。 活動があるところには、エントロピー、すなわち汚染が生じるわけだが、汚染 が増えっぱなしになってしまえば、活動そのものができなくなってしまう。 命を考えればわかりやすいが、生命活動とは、エネルギーを獲得しては老廃物 を生成させる営みとみることができ、老廃物は体内に汚染を引き起こす。 生きているということは、すなわち増えつづける汚染を体外に「捨てる」活動 でもあるわけだ。 「捨てる」という活動には、エネルギーも物質も消費するので、生きているも のはエネルギーと物質、すなわち資源を体内に取り込む。 そこで、今度は工業と農業をエントロピーという視点で眺めてみる。 工業生産という活動も、そこには必ずエントロピーが生じる。 資源を取り込み、製品を産み出す工業生産、工場で発生するエントロピーは、 廃熱、廃物として捨てられていく。 農業はどうか、農業も見掛けは工業と同じだが、捨てられた廃熱、廃物が自然 の中の循環機能によって、やがて資源として再利用される形となる。 この自然の循環作用から外れない限り、農業生産という活動は、資源の枯渇が 起こらないというわけだし、汚染も生じない。 ところが、生産活動によって生じるエントロピーを捨てる工業の場合はどうか、 自然の循環によってどれほどが資源として再利用できるだろうか。 資源として再利用できないところに生まれるのが、資源枯渇の問題であり、捨 てられた廃熱、廃物が引き起こす汚染問題、すなわち環境問題というわけだ。 (以上、「環境保護運動はどこが間違っているか?」第3章抜粋要約) 農業が「捨てる」ことになじまない営みといったのは、それが自然の循環作用 に逆らわない限り、資源枯渇や環境汚染とは無縁の、永続的活動が保証されて いるということなのだ。 本来、農業とはそういうものなのだ。 ところがだ、農産物の市場開放を国際正義のごとく要求する外圧、あるいは国 貿易で生きのびるためには(貿易黒字是正のための)農産物自由化やむなしと する内圧、そのどちらもがことごとく資源枯渇と環境汚染という次世代へのツ ケ回しを前提とした私利私欲の追求に走っているのだ。 おまけに、「お前たちも、俺たちを見習って、資源枯渇と環境汚染の共犯者に なれ」とでも言いたげに、やれ国際競争力だの、企業マインドなどとのたまう。 環境汚染の目安として、指標生物というものがあるのをご存じだろうか。 これは、きれいな環境にしか棲めない生物もいれば、比較的汚染の進んだ環境 でも平気な生物もいるわけだ。 従って、そこに生きている生物がどんな種類であるかをみれば、どれくらい環 境汚染が進んでいるかを間接的に知ることができるわけだ。 これにあやかって、そこに生きる人間の種類(人種ではない)でその国の環境 汚染度、資源枯渇度などが調べられるかもしれない。 少なくとも、農業と工業を同じものとしか見られない社会は、経済的にいくら 恵まれていたとしても、あるいは飽食の贅に明け暮れていたとしても、それは 廃熱、廃物のゴミの中でも平気で生きられる連中ではないだろうか。 農業をどう見るかは、すなわち人間がどう生きていくのかという分岐点でもあ るのだ。 資源として再利用できない活動を続ける社会では、汚染にもっとも弱い子供た ちにその影響が現れる。 食物アレルギー、味覚異常、呼吸器疾患、食の変質と環境汚染が次世代の担い 手に襲いかかろうとしている。 そればかりか、治水ダムの数倍もの貯水機能を果たしている山間地水田が、国 際競争力という詭弁のもとに決壊してしようとしている。 それでもあなたたちは、水害と疾病の嵐の中で、さらにエントロピーを増大さ せていこうというのか。。 農業の変質は悲しい、悲しい農業は飢えを救えはしないのだ。 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
先頃、経済界の声をマスコミに大きくアピールする「コメ市場解放」広告がだ されたり、農業を経済生産性という切り口で切り刻もうとする一団のパフォー マンスは相変わらずである。 自分たちがどんなものを口にしているのか、教えられてびっくりする人にはま だ救いを感じるのだが、国産であろうが輸入品であろうが、そんなものどうで でもいいじゃない、なんてまったく「消費者」になりきってしまう方々にはな んとも言葉のかけようがない。 まぁ、人それぞれに選択の自由があるわけだから、日本の農業なんてどうでも いい、という人がいても不思議ではない。 ただ、日本の農業、ちょっとでも「がんばって欲しいな」という気持ちをお持 ちの方々がいらっしゃるなら、僕たちはそんな人たちのために「よし!」とい う励みが生まれることもつけ加えておきたい。 農業生産の側にいて、どうにも不可解な「農業従事者団体」のふるまいに憤懣 やるかたない思いにかられることがある。 マクロでは国内農業保護を訴えているようで、ミクロでは産地のつぶしあいに 敵味方の市場争奪線をくりひろげてみたりする。 市場での信用獲得のために、一定規模の生産を一定期間持続できるだけの生産 計画がたてられ、そのためには連作、過作をいとわず、責任出荷なる隣組制度 まがいの組織半強制が日常茶飯事になったりする。 営農指導と称して、情報がいつも内へ内へとしむけられ、あたかも農業という 営みが「生産」というワンウェイの業態であるといわんばかりの風潮を自らが つくりだしている。 だから、「生産性の劣った農業なんかに補助金をだすことは、税金の無駄使い」 なんて言われても、確かに儲からない国内農業、無理して土地にしがみつく必 要もないか、なんて後継者予備軍離脱の下地がその声を道理として容認してし まうことになる。 「旦那、ちょっと待っておくんなさい」、時代劇なら聡明な岡っ引きが一見落 着にみえる事件に一矢をあびせるものだが、どうも「農業」がすっかり飼い慣 らされてしまったのか、それとも悪代官に賄をにぎらされてしまったのか、さっ ぱり「ちょっと待った」の声が大きくならない。 農業は農業だけ、消費者は消費だけ、実に巧みに「囲い込まれ」てしまってい るのだ。 内に向かってひたすら守りの体でちぢこまらずに、あるいは同士討ちよろしく 産地のつぶしあいにばかり眼を奪われず、もっともっとダイナミックに循環と してる「農」を思い起こしてみてはいかがなものだろうか。 誤解があってはいけないのでもうし添えるが、この言葉は業界の内部啓蒙なん かじゃなく、俗に「消費者」と呼ばれている人たちもひっくるめての話なので ある。 「あたしゃ食べる人、百姓なんかと一緒にされちゃいやだよ」とおっしゃらず に、ぜひとも「生産者」の仲間入りをしていただきたいのだ。 まず、日本は資源のない国だから、資源を輸入して工業生産で生計をたてる、 土地生産性のうえで、比較優位たりえない農業など不必要、この論法を検証し てみる。 資源はほんとうにないのだろうか、資源を輸入にたより、そしてひたすら利潤 の追求に奔走してきた日本、その人口バランスをよーく見て欲しい、その構成 はピラミッド型から釣り鐘型、そして今度は逆三角形になろうとしている。 ひたすら物質的充足を工業化によってはかってきた結果が、実は労働人口の減 少となる、しかも経済成長期にせっせと食品添加物の御世話になった世代が、 粗食によって長寿を迎えている今の老人たちにとってかわる時代に、はたして どれだけの「長寿」を望めるかといえば、実に心許ない限りではないか。 かくして、50年先の日本は資源がなくても十分に「食べていける」国に落ち つくはずなのだ。 では、「今」はどうなのか。 「資源がない」という割には、ずいぶんと資源のムダ遣いに明け暮れている。 安く資源を買って付加価値で稼ぐのだから、そんなムダ遣いもできてしまうの だろうが、麻雀を参考にするまでもなく、儲かったやつがいれば、かならず損 をしているやつが生まれるものなのだ。 一人勝ちが続くためには、その勝ちを支える割にさっぱり浮かばれない諸国が たくさん存在することも事実なのだ。 そんな一人勝ちの論理で、農業が同じ土俵に入り込もうとするところに落とし 穴が生まれる。 ひと昔前の肥溜め農業から、石油化学工業にすっかり囲い込まれた化石燃料依 存型の使い捨て農業にはまり込んでしまう。 これじゃ土地はどんどんと疲弊していくし、土壌中にあった潤沢な微生物の資 源もまたたくまに貧困の際に追いやられてしまう。 これじゃ、せっかくの「資源」を食いつぶしながら「資源なんてどこにもあり ません」と言っているようなものである。 それでも懲りずに、化学肥料輸入の御片棒を担いで、農薬のふりかけで「需要」 に応えては、けなげにも「弱体農業」のそしりに甘んじてみたりする。 驚くは食料の海外依存を是とする「私、食べる人」がせっせと大量消費にいそ そみながら、資源がない、資源がない、と自己暗示にかかってしまっているこ となのだ。 生産する方も、消費する方も、いつの間にか一方方向でしか世の中が見られな くなってしまっている。 これほど大量に世界中から食い物をかきあつめていながら、どうして「資源」 がないといい続けられるのか、それでいながら「有機野菜」には特別な魅力を 感じるらしく、「有機、有機」とワンランクアップの大合唱がはじまる。 工業化社会で大きく変わってしまったのは、「消費=使い捨て」という意識の 蔓延ではなかっただろうか。 捨てることが当たり前と思いこんでしまえば、それこそいくら資源があっても 足りるものではない。 逆に、資源がないという思いこみをさせるために、「使い捨て」の消費様式が 利用された、おっと、これは大胆するぎる仮説なか。 農業を例にするなら、江戸時代の農業とは「肥溜めくみ取り循環型」という、 世界に誇れる生産−消費サイクルであったわけだが、化石燃料依存の今日では、 「下水流し去り喰い逃げ型」という文字通り一方通行農業なわけだ。 金にものを言わせ、世界中から集めまくっている食料資源がまたたくまに下水 とともに去りぬ、おお、これぞ使い捨ての極み! こんなことでは、20世紀文明がかきまわした気象異常というツケに、果たし てどこまで食糧資源を集められるものか、生産者も消費者も意識転換をすぐに でも行う必要があるのではないだろうか。 まずは、「消費者のみなさん、ぜひとも生産者になって下さいな」。 農業には、大都市が生み出す大量の有機物資源が実は利用できるはずなのです よ。 大量の生ゴミ、これが埋立に使われるやっかいものなら、ぜひとも農地へ戻す 運動を始めてください。 できるなら、下水料金を払ってまでして始末している排泄物、もっと有機物と しての価値を高める努力をしていただきたいわけです。 そうすれば、あなたたちが見捨てようといている化学肥料でやせ衰えた大地に かつての豊かな微生物たちが資源としてよみがえります。 そうなると、農家もあまり農薬の御世話にならなくて済む農業が可能になりま す。 そこで生産される農産物は、決して農家だけの生産物ではなくなりますし、農 家はある意味で都市圏生産物の消費者となることにもなるわけです。 となると、消費者とばかり思いこんでいたみなさんは、農業における生産者に も十分なれるわけで、実はこれが本来の農業という営みなんじゃないかと僕は 考えるわけなんですね。 産直とは、既存の流通からの農家の意識脱皮でもあるわけですが、生産−消費 という流れから見ると、まだまだ一方向的であると言わざるをえません。 あたかも、川は上流から下流へ流れる、その流れだけを見ているようなもので す。 ところが、川を流れる水を上流へたどると、やがてその内の一本は源流にたど りつく、ではその先はというと、実は海へ流れ下ってしまったと思いこんでい た水が大気の循環という大きな流れによって源流にまい戻ってきていることを 知るわけです。 たぶん、僕も、そして都市生活者のみなさんも、ただ呆然と川縁に立って水の 流れを上から下へながめているだけの人間なのじゃありませんか。 農業も、水の大循環と同じように自然の営みの中で存在しているものです。 生産が生産だけに、あるいは消費が消費だけに囲い込まれてしまうことは、恐 らく流れをせき止めるダムにせっかくの循環が遮られてしまっていることなの じゃないでしょうかね。 僕たちは農作物をつくる生産者だけではなく、よき情報提供者でもありたいし、 よき有機物消費者でもありたい。。 どうか、都市生活者のみなさんも「農業」という循環産業の一方の生産者となっ て下さい! 生ゴヨよ、農地に還れ! 資源よ、ゴミに埋もれることなかれ! 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
中野孝次著「清貧の思想」を読んだ。 古典にみる清貧に生きた人々の姿、そこに見る人の生きざま、生きることの充 実とは何か、心洗われる思いがした。 中野さんは自らの人生を顧みて、敗戦の昭和20年に20歳だった意味を壊述 されている。 一面焼け野原となった首都東京、その荒廃の貧しさの中から10年後に、貧し いながらも四畳半と六畳二間しかない団地に住めるようになった時の喜び、そ の後の高度経済成長と欲望の対象の増加。 中野さんの生きてきた3つの時代、その中から中野さんは故人が古典の中に書 き残してくれた真の幸福とは何なのかという智慧を深く噛みしめているのであ る。 高度経済成長期からのわれわれの生き方に触れた次の一節を引用する。 「街には商品が溢れだし、クルマでも電気機器でも住宅でも次から次へ新製品 が作られ、魅力的な広告によってわれわれの欲望を刺戟しだしましたから、そ のころからわれわれは絶えざる欲望のとりこになって、新製品を追いつづけて 来たような気がします。そしてわれわれはただの人間ではなく消費者という名 で呼ばれるようになっていきました。」(p.204) 中野さんは、「消費者というこの人間侮辱的な言葉」と表現されている。 消費者というものを人間侮辱的と評すること、あまりに当たり前に消費者を主 張してはばからない現代では、どこが侮辱的であるのかがいぶかしくもあるだ ろう。 ただしかし、自分が消費者であることに何の疑問を感じない現代人でさえも、 間近に世紀末を迎える段となって、大量消費のもたらす物欲への充足とさらな る欲求、物で満たされているようでいて豊かであるようでいて、満たされきれ ない空しさ。 なぜリサイクルに関心が向くのか、なぜ環境問題に不安を感じてしまうのか、 漠然とした時代の転換点を意識しはじめている。 「清貧の思想」に登場する卓越した先人たちの言葉に、自分が自分であること の新鮮さを、しかも数世紀を隔ててなお生き生きと感じるのはなぜだろうか。 貧しさの対局にある「富み」とは、人間にいったい何をもたらしたのか、貧し さをうしろめたいもの、恥ずべきものと一蹴してしまう感性こそが、実は心の 貧しさなのだと教えてくれる。 大量生産社会がはたして人間にとっての心の豊かさにどれだけ配慮されたもの だったのか、この素朴な問いに消費者を自称する生活者たちはどう答えるだろ うか。 清貧という思想が脈々と息づいてきた日本、たぶんそれはあらたまってリサイ クルなどと気張らなくとも、それが当たり前のものとして暮らしの中に実践さ れてきたことだし、人間が特別なものとして突出することなく、自然の中につ とめて一体化しようとしてきた風土的遺産に違いない。 その自然との一体感が日常の生活から損なわれてきてしまった最先端に今の消 費社会、物欲への執着がある。 古事に見るまでもなく、富、権力、名声に生きた人間たちはいつの世にもいた。 その一方で、富に溺れるな、権力に奢るな、名声に踊るな、という処世の律が たしなめられてもきた。 生き方を自らの内から律するという心持ち、それが良い悪いというのではなく、 あるかないかということなのだ。 中野さんは、たぶん今の世代への期待の意味もこめて、次のように述べておら れる。 「日本には、かつて清貧という美しい思想があった。所有に対する欲望を最少 限に制限することで、逆に内的自由を飛躍させるという逆説的な考えがあった。」 (p.138) 内的自由とは何か、ものの豊かさ、旬をわざわざ表示しなければならないほど 季節感がなくなってしまった食べ物、その豊かさに囲まれてながら、あくせく と働く、絶えずもの・富・権力のために心理的に圧迫された毎日を送る。 そして、そうした圧迫からの開放をあからさまに口にせずとも、うすうすと意 識しはじめている。。 「清貧」、この言葉にはうしろめたさはないし、四季のうつろいに従順に生き てきた文化の神髄が感じられる。 四季のうつろいを映像でしか見つけられない生活空間の中で、自然と一体となっ て生きることの豊かさを味わうことは難しいかもしれない。 一人一人がなにかしらものだけでは満たしきれないものを感じながらも、消費 社会(大量生産社会)の歯車として走り続けねばならない現実を大事に、経済 大国という響きを励みに時流に流れていく。 まして、自らを消費者と称することになんのためらいも感じないことが、本当 に人間らしい姿なのかどうか。 物質的繁栄といっても、それは富める国、貧しい国が表裏一体となっての、し かも富める国だけが語る言葉である。 富める国といっても、そこに生きる人々がすべて富にあずかっているのではな いし、作っては所有する、所有しては捨てる、そしてまた所有するというもの の豊かさを無限音階のように繰り返しているに過ぎない。 ところが、そこに内的自由がないことに気付き始め、無限音階が幻聴にすぎな いことに目覚め、生活者とは何かを考え始めた。 生活者にとって生産とは何か、消費とは何か、豊かさとは何か、なぜ争いは絶 えないのか、自分にできる範囲で問いなおしてみる時期なのかもしれない。 そして、それが物質消費、所有からの後退であっても、豊かさへの前進のため なら敢えてリストラクチャーを惜しまない実行の時なのかもしれない。 清貧の思想とは、四季への郷愁を求める今日社会に生活の豊かさとは何かを見 つめ直すため先人の遺産なのだから。 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
僕の妹は、帯広市内の総合病院に勤務する看護婦であり、その病院は地域の中 核病院として患者が集中する。 看護婦の絶対数の不足が医療現場でどれほど深刻な問題なのか、たまに実家に 野菜補給に帰って来る妹が、「たまの休みでも、くたくたに疲れて外に出る元 気も出ない」なんて話を聞かせてくれる。 地域のセンター病院として患者がドッと集まってくることも多忙に輪をかける 原因なのだが、夜勤も含めた過酷な勤務実態が少ない医療スタッフの手によっ て支えられている現実を当該地域の住民のどれほどがおもんばかっているだろ うか。 恐らくある日、自分が病院のご厄介になってしまった時に、地域医療と医療従 事者の問題を痛いほど思い知らさせるに違いないのだが、多くの人は病院のお 世話になるという仮定を目一杯「他人事」のように深く考えようとしない。 にもかかわらず、病気になると「どこそこの病院は大きいから」なんて、まる でなんとかの一つ覚えみたいに特定の病院に突っ走る。 十勝みたいにちょうど地域のど真ん中の都市ができあがっている処では、さな がら漏斗のように患者が集まってくるし、しかも総合病院の看板に病人が殺到 する。 地域医療の問題は、医療従事者の数の問題もあるが、地域の病院間の役割分担 がうまくいっているか、いないかの問題と切り離して考えるわけにはいかない。 慢性の患者さんをケアーする病院、急患をケアーする病院、一次医療、二次医 療間のネットワーク、それをどう役割分担するかによって地域医療はより患者 の側、ケアーする側にゆとりのある医療を提供できるに違いない。 それをネットワークというしくみにだけ頼ってしまいがちなのが、ある日突然 病気にかかって慌てふためく「おろかな病人」の常である。 これは、システムで解決しきれる問題じゃなく、病人予備軍としての自覚とそ のための備えをしておく「地域住民」自らの問題ではないだろうか。 すなわち、「ホームドクター」である。 健康保健の税額にはピリピリしがちだが、医療費負担額が増加する背景には、 病気になってしまってから「慌てふためく」病院の利用の仕方にかなり問題が ありそうだ。 転ばぬ先の杖、「病気になってから」よりも「病気にならないための努力」を もっと心掛けておけば、医療負担額は自ずと軽くなる。 すぐに「制度」の問題に責任転化してしまいがちな「小市民」だが、案外ホー ムドクターという「備え」を実行している人は少ないのではないだろうか。 対症療法的医療から予防医療へ、これは自己防衛の一番の切り札でもある。 欲を言うついでに、新しい防衛方法を紹介しよう。 それは、「ホームファーマー」である。 偶発的な、例えば交通事故みたいなけがはどうしようもないが、あっ、これは いくら運動神経をきたえても避けきれないという意味でね、いわゆる病気とい うやつは日常の生活の仕方に原因がある場合が少なくない。 寝不足、酒、たばこ、これは「わかっているけど、やめられない」自覚型の原 因ともいえるが、世の飽食ムードと裏腹に、「医食同源」という先人の教えは ほとんど自覚がないのじゃなかろうか。 疾病のタイプにも、どうも「昭和30年代型」、「昭和40年代型」があるみ たいで、高度経済成長期を境に、日本人の食事の内容や摂取カロリーが炭水化 物型から脂肪型へ、いわゆる欧米型の食習慣へシフトしてきていることに大き く関係しているらしい。 「やめられない、とまらない」のキャッチコピーが一世風靡し、ファーストフー ド、ファミリィーレストラン大はやりという世相に伴って、若年性成人病なん ていうおかしな病気が増えてきた。 中年過ぎのおじさんたちは、おなかのでっぱりと運動不足に「糖尿病予備軍」 の不安を抱え込むようになってしまうし、「肝心」の語源どうり、肝臓と心臓 の変調についつい過敏になってしまう。(おっと、心労の胃と十二支腸ストレ スは現代人の常識か) 消化器、循環器へのストレスが成人病の根源なら、医食同源の教えを見直して 「食いあらため」ればいい。 そんな時、きっとお役に立つのが「ホームファーマー」である。 自分達の食事へ安全な食材を提供してくれる信頼のおける生産者、すなわちお 百姓さんを見つけておくこと、これすなわち「ホームファーマー」である。 農業がどんな存在であるのがもっともよいのか、そりゃ、生活の場所に近けれ ば近いほどいい。 しかし、都市空間、農業生産空間のバランスが著しく偏ってしまい、しかも、 都市近郊から農業が追い出されていく現実では、「ホームファーマー」を確保 するというのはとても難しい。 でも、難しいと片付けてしまうのと、病人、半病人で生活を制限され、しかも 高額の医療費負担を強いられるのと、はたしてどちらがお得だろうか。 (注:筆者は、みかけの損得で話をすることに抵抗を感じる人であるとを申し 添えておく) 繰り返すが、農業は生産が消費の直近にあればあるほどいい、それはお互いが 食の安全に目をくばることと同時に、食べてくれる人、生産してくれる人を意 識できることによって、精神的な喜びがもたらされるからだ。 「そんなもの」なんてバカにする向きもあるかもしれないが、知らない人、知 ろうとしない人に限って「バカ呼ばわり」するのが、これまた人間のあさまし い性である。 僕や僕の知人は、その喜びを知っているから、それがわかる。 医学的メカニズムのほどはわからないが、この安心というか喜びというか、そ れをもたらすものは農業が本質的に持っている刺激ホルモンなのじゃないかと 思うのだ。 食べ物とは、本来そうした関係を成り立たせてきたものだろうし、いくら無農 薬だの有機栽培だのと言ってみたところで、そのホルモンの恩恵にはあずかれ ないに違いない。 つい先日、フランスの景観工学のスペシャリストの講演を伺ったが、その中で 「都市の回りに森をめぐらしたところで、都市に住む人は本当にその森に出か けるだろうか。都市の回りに森をめぐらすのではなく、都市の中に森を引き込 んでこそ、ある人は自転車で、ある人は犬を連れて散策しながら森へ出かけて いけるのだ。」 というお話があった。 これには感激した。 「森」を「農業、農村」にそっくり置き換えてみると、今の都市と農村、そし て食の抱える問題が鮮明になってくるように思える。 成人病に怯えるよりも、田舎に「他人の親戚」を一人でも見つける喜びの方が、 はるかに健康な暮らしのように思えるのだが、いかがなものだろう。 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
「ポストハーベストアプリケーション」、この言葉は農作物収穫後の品質保持 のために施されるすべての措置をさして用いられる言葉だが、一般にポストハー ベストというと日本では「収穫後に使用される農薬」として用いられている。 農産物の貯蔵倉庫で働く空調とか温度調節も、ポストハーベストアプリケーショ ンだし、例えば国内でただ一ヶ所、イモに放射線を浴びせて発芽を抑制してい る士幌農協の馬鈴薯貯蔵も、厳密には「ポストハーベスト」ということになる。 それから、収穫以前に施される品質確保のためのいろいろな措置のことをプレ ハーベストアプリケーションと呼ぶことにすれば、「農薬の使用」と狭義に用 いてそのお世話にならない農作物はほとんど存在しない。 「ポストハーベスト」という言葉が農薬にばかり張り付いてしまうのは、それ だけ農産物の安全性に対する関心が高いことの表れかもしれないが、言葉が一 人歩きしてしまうことの危うさも逆に心配になってしまう。 物事は一面的に眺めていては、実態は見えてこないものだ。 「ポスト」もあれば「プレ」もある、農薬もあれば空調もある、食べ物への残 留の危険を叫ぶ主婦もいれば、その農薬をもっとも高い濃度で体に浴びながら 作業をしている生産者もいる。 自分だけの「側の目」で眺めてしまうと、被害者はいつも自分だけになってし まう。 だからといって、ポストハーベスト農薬に免罪符が与えられるかといえば、そ うではない。 食料自給率が3割を割ってしまっている日本の食料事情では、好むと好まざる とにかかわらず、ポストハーベストの洗礼を受けた食品が我が口に取り込まれ ていることになる。 輸入食品の9割が書類審査のみで通関している現実、植物検疫の人員が手薄な こともあるが、なにより膨大な量の輸入農産物・輸入食品が我が国に押し寄せ てきているのだ。 もし9割の書類審査通関の輸入農産物の中に、書類内容と偽りのあるポストハー ベスト農薬が施されているものがあったなら・・・、そんな心配をしはじめる と際限がない。 消費者団体がポストハーベスト農薬に対する監視の目を求めるのは、それだけ 実態の掴めない輸入食料が原形を留めない形で食卓に上がり込んでいるからに 他ならない。 もちろん、国内生産者団体も農産物貿易自由化への抵抗のために、さかんに輸 入農産物の安全性についての意識啓発に力をこめている。 でも、ちょっと待てよ。 農薬は、「ポストハーベスト」だけの問題だろうかと。 農産物への農薬残留基準は確かに厳密かもしれないし、農薬に依存しなければ 市場需要をまかないきれない農業の現実もある。 では、「国産農産物はポストハーベストの心配がありません」と訴える日本の 農協が、「私の農協では、一年間にしかじかの農薬売り上げ実績があります」 とどれだけ公表しているだろうか。 個々の市場流通銘柄に「減農薬」のアピールがされていても、どう農薬が減ら されているのかを知るのは多難なのだ。 客観的にそれを定量するすべは、個々の農協が農家への農薬売り上げ実績を定 期的に公表していくことではないだろうか。 ポストハーベスト問題を真剣に扱うのであれば、プレハーベストの実態につい ても真摯に伝える姿勢がなければフェァーではない。 農業情報とは、作る側の利益のためにのみあるわけではないのだし、農産物を 求めてくれる人のために、文字通り「なさけにむくいる」ものでもあるのだ。 もう一点、農業者の側が声だかに「ポストハーベスト危険」を日本農業の防波 堤のように叫ぶこと、防波堤は高波に対しては有効であっても、それを乗り越 える大波には無力であることにも目を向けるべきなのだ。 例えば、ポストハーベスト農薬の最右翼、くん蒸処理に対して、農薬の変わり に二酸化炭素を用いて害虫を窒息させる処理方法が商品化されようとしている。 ポストハーベスト問題があまねく「克服」され、安全性に問題がなくなってし まえば農産物はすべて輸入でもいいのか、農業生産者が自国農業の存在意義を 訴えかける核心は、ポストハーベスト農薬にはないはずなのである。 なぜ農業がその国にとって必要なのか、生産者も消費者も共にこの切り口を見 失ってはいけない。 もちろん、その実態が明らかにされない農産物輸入、あるいは国内で使用を禁 止された農薬が第三世界に輸出され、その国で使用され輸入農産物のかたちで 舞い戻ってくる「ブーメラン現象」、このポストハーベスト農薬にまつわる問 題は根絶やしできるほど単純ではない。 ただ、ポストハーベスト問題は枝葉にすぎないのだ、根幹は命と人にある。 枝葉に心を奪われると、多くの生命を宿す森の姿、鳥のさえずりは聞こえてこ ない。 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
今年の北海道農業は、天候不順に泣かされている。 7月のはじめにやや持ち直した天候も、中旬以降は曇天の肌寒い日が続き、夏 の声はどこかへ行ってしまったままである。 官庁が発表する作物の作況も軒並み10日以上の遅れとなっていて、この時期 の生育の遅れは今後の天候回復があっても取り戻しきれない。 天候異変が語れはじめて久しいが、暖冬と冷夏、この傾向はますます顕著になっ てきているような気がする。 暑中御見舞いのお便りもいただく昨今だが、「暑さ」のおすそ分けをぜひ!、 なんていうのが偽らざる気持ちでもある。 作物には固有の生育パターンがある。 植物学的には「栄養成長期」と「生殖成長期」の2つのフェーズが日長と温度 によってコントロールされているわけだが、この気象条件が狂いはじめると成 り立たなくなってしまうのが近代農業のいう「計画生産」ということになる。 十勝農業は、基幹となる豆・馬鈴薯・甜菜・小麦に加えて、最近は広く野菜が 導入されるようになっているのだが、こうした多種作物を4月から11月の短 期間で作付け・収穫できるのも、実は個々の作物の生育パターンに対応した絶 妙の労働力配分が前提となっている。 もし、この生育パターンが崩れるとどうなるか、労働力は家族労働プラス雇用 労働、しかも雇用労働力、俗にいう「出面さん」が高齢化やリタイヤしてきて いる現状ではその確保もままならない。 となると、あちこちで農作業の競合状態が起こって、病害と雑草との戦いに追 われることとなる。 こんな年は、苦労ばかりが多く、豊穣は見込めないというなんともやりきれな い出来秋を迎えることが多い。 いつもならとっくに開花しているはずの小豆であるが、畝の半分にも広がらな い枝葉が連日の低温に震えあがっている。 年明け後の和菓子の価格も気になるところだが、農業収入に依存する百姓の懐 は他人ごとではない。 塞がらない畝間には、これ幸いにとばかり雑草が大きな顔をもたげる。 除草していても、からっと晴れればすぐに天日でひからびてしまう雑草も、湿 潤な天候ではまた根付いてしまう。 除草剤という農薬にしても、そのほとんどが生育期では選択性のものしか使え ないので、ある雑草は押さえられても他の雑草にはまったく効力がない、つま り「手作業」に頼るしかない。 例えばトウモロコシ、この作物は典型的な「積算温度型作物」である。 生育期の平均気温がトータルで何度ないと実が入らない、そんな作物なのだ。 連日、「低温注意報−日平均気温が平年よりも4度以上低い日が2日以上続く」 が出ているようでは、路地もののトウモロコシの出まわりはまさに直撃を受け てしまう。 今朝のニュース解説では、太平洋高気圧の勢力が弱く、7月に本土上陸のコー スをたどる台風の進路は例年よりもかなり東にズレているとのことだった。 ということは、例年西日本に被害をもたらす秋の台風、今年は東日本にズレる 可能性が大きいような気がする。 冷夏のために経済活動にも影響が出て来ているようだが、曇天を一番うらめし く思っているのは、作物たちに違いない。 いつもなら収穫の半分にさしかかろうとしている秋まき小麦の収穫も、十勝で は8月5日を過ぎて始まるかどうかという状況である。 それまでの降雨によって、倒伏と穂発芽という小麦にとって致命的な被害が出 なければよいのだが。 野菜の高値にため息をついている主婦も多いと思うのだが、天候不順に草取り に追われる生産者のため息もまたしかりなのだ。 自民党政権が下野するらしい国政の動き、出来秋に期待できない農民たちにとっ ては農産物市場開放や政府支持価格の動向にもより敏感になってしまう。 旧野党大連合とはいっても、市場開放勢力が国会の2/3になってしまってい る実際では、選挙戦で各地で「コメの市場開放には断固反対します」といって 当選していった議員たちの「その後」も気にかかる。 気にかかると言えば、アメリカ・ミシシッピーの大洪水、インド北部の大洪水 と、世界的な農作物被害の影響も気になるところだ。 コメの市場開放問題では、日本も「開放やむなし」に傾きつつある雰囲気だが、 当のアメリカではアジアからの移民の増加によりコメ需要の増加と生産地帯で の水資源の逼迫から、「これからは輸出どころではない」というのが生産者の 声だという。 食料自給率が今回の政権移行で今後どうなっていくのか。。 そんなことを「新聞記事、テレビニュース解説」で聞き流すようなライフスタ イルでは、農業の生産現場での食糧生産についての危機感は決して「自らの問 題」とはなりようがないかもしれない。 話はそれるが、今十勝には9人のチェルノブイリの子供たちがやってきている。 僕の友人宅にも3人の子供たちがひと月のホームステイをしている。 このプロジェクトには、たくさんの仲間たちが参加しているのだが、なぜチェ ルノブイリの子供達が日本にやってきているかを知っていただきたい。 その目的は「放射能の高汚染地域に暮らす子供たちに放射能から切り離した生 活を送らせてあげるため」であり、「汚染地域の弱化している免疫システムが、 一ヶ月間でも放射能から離れて健全な食生活を送ると、その後半年か一年は免 疫システムが正常に機能することがわかっているため」なのだそうだ。 そのために、十勝にやってきている子供たち(9才〜11才)にも、当地のメ ンバーが健康に育てた野菜などを提供している。 加工食品の氾濫で、食べ物の価値を水や空気みたいに当たり前のものとしか感 じられなくなった人が結構いるかもしれないが、健康な食生活が健康な免疫シ ステムを支えていること、どうかわかっていただきたいものだ。 ひと月後、子供達がどんな顔色になって帰っていくのか、とても楽しみなのだ。 このプロジェクトを支えている「チェルノブイリへのかけはしプロジェクト十 勝事務局」(まったくのボランティア集団)では、この支援活動のための募金 活動(子供達の旅費、滞在費−食費・交通費)も合わせて行っている。 もし、賛同(機関紙ではあえて「参同」になっている)していただける方がい らっしゃれば、募金活動に参加していただければ幸いである。 郵便振替口座 小樽1−1538 口座名 チェルノブイリのかけはし十勝 名ばかりの「ネットワーク」があちこちに乱立する時代だが、こうしたネット ワーク活動には「人のあたたかさ、そしてパワー」の共感を覚える。 市民ネットワーク時代の萌芽が、次の時代に実を結ぶ気がしてならない。 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
農業が「農」と「業」の2色の混ざりもので、「業」でまわりの世界と比較さ れると「食っていけるか、いけないか」、「食わしていけるか、いけないか」 という生き残り(勝ち残り)意識が「農」の温もりを奪い去っていく。 食い物を自らの手で生産している百姓が、「食っていけるか、いけないか」、 「食わしていけるか、いけないか」に悩まなければならない、、でも、この話 ちょっと変じゃないか、不条理じゃないかと感じる農民の目覚めが「農」に温 もりを取り戻してくれるだろう。 農業の「業」は、工業・サービス業の「業」ではない、自然の恵みを命の糧と して生き物に与え、「むら」という共同体を育み、そして健やかな次世代を育 てる、「育てる」わざが「農業」なのだ。 ところが、この育てるわざが「育てる必要のないわざ」、「誰かが代行してく れるわざ」に取って代わられてきたところに、農業の疲弊がある。 アパレルでは常套の「ブランド」、マーケッティングの名のもとに農産物が名 前で一人歩きを始めてしまうのは、消費者を育てるわざを他人に委ねてしまっ た証しではなかったか。 その結果、各地の地方色豊かな在来種が大手種苗提供の特定品種に置き換えら れてしまったし、「ブランド」が産地イメージの立役者になってしまった。 確かに産地は「ブランド」でもいい、でも、それを作っているのは誰なんだ、 産地は脚光を浴びても、それを生産する農家がスポットライトを浴びるどころ か、絶えず追いまくられる舞台裏に置かれるのはなぜだろうか。 都会人たちのアキレス腱は「食い物を自給できないこと」にあるのだが、食い 物を「買ってやっている」という論理でそれをカモフラージュしようとする。 では、「農民たちは、食い物以外のものは自給できるのか、それらは私達(都 会人)がいなければ手に入らないものではないか」、その通り、農民にもアキ レス腱はやはりある。 大切なのは、「お互いにアキレス腱を持った生身の人間である」ことを認め合 い、あるいは知り合うことにあるのではなかろうか。 ところがだ、経済発展の過程で農民は「産地」に、都市生活者は「会社」に、 それぞれが身を委ね過ぎてしまった。 農産物は自動車部品のように「物流の一つの部品」に組み込まれてしまったわ けだ。 原価と製品(商品)価格の差、つまり利潤の追求という経済行為と、節度なき 原料調達が組み合わされてしまうことの悲劇、「産地」や「会社」は姿を変え て生き残っても、それを支えてきた人間の労働は「代替部品」の一つにすぎな い。 農産物の自由化反対を事ある毎に叫びつつ、自分たちの手塩にかけた農産物を 「部品」扱いに甘んじさせてきた覚えはないのだろうか。 一世代四半世紀、今の大人達の選択が孫子の存亡に関るというのが、膨張を続 ける地球人口と破壊の続く地球環境時代にあっての食糧生産の姿であり、問題 点なのだ。 生産性の向上を多肥と農薬と農業機械、それに適合した品種の作出に傾注して きた「農法」は、やがて資源の行き詰まりと食糧の奪い合いを招く運命にある。 農産物が「部品」となってしまったつけの予兆は、経済発展の優等生「日本」 で心配されていた経済の空洞化が現実のものとなり、「会社」は存続のために 「社員」は切り捨てられ、技術立国のための投資も海外に流出する、アキレス 腱をなるべく見ないように働いてきた生活者たちは不況風の凍える。 「コメの自給」にしても、では「コメ生産の何割が自まかないで行われている のか」から見てみると、種モミと農家労働、そして水田くらいのものじゃない だろうか。 肥料の大半はすでに国外依存状態だし、農薬にしてもしかり、生産資材はその ほとんどが「外国産」由来。 水田のエネルギー収支では、いや、日本のほとんどの農業のエネルギー収支で は、「自給」などとっくに崩れ去っているわけだ。 「コメの自給」が生活者の胃袋でだけ論じられてしまうと、「精米が国産か輸 入米か」という「コメ問題」に終わってしまうが、コメの自給を部品ではない 「農産物」で考えていけば、そこには化学肥料になるべく依存しない、農薬に なるべく依存しない、エネルギー収支からの自給の姿が見えて来る。 「コメの自給」といった場合、その主語は何をさすのだろうか。 「日本人」なのか、「私達」なのか、普段は作り手のことにまったく関心を払 わないできた「コメ(食料)」が、流通環境が切迫してくると同時に「私達」 を語り始める都合よさはないだろうか。 農業補助金批判しかり、生産性批判しかり、さらには3Kというレッテル、そ れでも農業者は年間1〜2作、生涯に数十回しかできない実りの収穫のために 働いている。 農業者が不労の蓄財を補助金によってしているのだろうか、自由な生産資材調 達ができる環境で低生産性のそしりを受けているのだろうか、だが、批判の側 に回るものの多くはその実態のいかほども知らない。 農薬残留をPPMレベルで気にする人は、その何千倍もの農薬使用環境に置か れている農民たちのことを気遣っているだろうか。 「自給」とか「食料」を口にするには、その時だけの「わたしたち」じゃなく、 普段から「わたしたち」と言い合える間柄になっていなければ、わだかまりや 不信はいつまでたってもぬぐい去る事はできない。 農業は「ひとをそだて、いきものをそだてるわざ」なのだから、それがおかし いと感じた時には「ちょっとおかしいよ!」と誰彼となく声を発しなけば。 本当に「自給」を「わたしたち」の問題として意識し、農業を「そだてるわざ」 として理解し行動していける人間関係づくり、これが「業」で語る「農」でな いがしろにされてきた共生の思想につながるのだろう。 「論」で通じ合った人達が、次にどんな行動に思いを馳せて行くのか、このも う一転がりがなければ「責任のなすりあい集団ヒステリー」時代はいつまでた っても終わらない。 屋上屋を積み重ねるよりも、一から作り直した方がいい場合だってあるのだし。 十勝 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
帯広に出かけた帰りに、ふと書店に立ち寄って店頭に並んだ「現代用語の基礎 知識1994年版」をめくってみた。 用語索引の「テ」の項を追っていくと、太ゴシックで「電直」の項があるでは ないか。 1068ページを開くと、1993年に巷で流行った言葉の中に、「電直」が 載っていた。 僕は思わず、言葉にいいつくせない感慨にひたった。 1988年にSIG「グローバル・ビレッジ」のフォーラム「スペシャル・プ ロジェクト」で始まった僕の【電直】とのつきあいが、とうとう現代用語とし て5年の歳月を経て認知されたわけだ。 半分冗談、半分本気で、仲間たちと「現代用語の基礎知識に載らないと、【電 直】は半人前だね」なんて語り合っていたあの頃。。 僕の心の片隅には、「いつかは、現代用語の基礎知識に」という願いがいつも あったし、新年度版が書店に並ぶたびに「ああ、今年も載らなかった・・・」 と肩を落としたものだった。 用語解説には、パソコン通信による相互交流であること、そして産直の新しい 形であることが記されている。 わずか数行の用語解説がどれだけ「電直」の世界をまだ知らない人たちに伝え るものなのか、でも、そんな事は知の楽しみにふける人向けと割り切ればいい。 この5年間、僕たちやその仲間たちがコツコツと地道に活動してきたことの証 しが、「言葉の認知」という顔を得たということなのだから。 もちろん、僕達のネットワーキングへのこだわりは「電直」ではなく、あくま で共生の思想に根差した生産と消費の循環、誰もが生産者・誰もが消費者、そ して「他人の親戚」関係を築くための【電直】であることに変わりはない。 「産直の新しい形」は「産地直送」ではなく、「(知的・物的)生産者たちの 直接交流」、すなわち第二世代の「産直」ではないかと思うのだ。 言葉の認知を励みに、点と点のネットワークから面と面のネットワーク社会を 目指して頑張っていきたい。 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
低温と日照不足、1993年の日本の農業は100年に一度か二度という冷害 に見舞われた。 特に、東北の太平洋側から北海道にかけての北東気流の流れ込んだ地域は、作 況指数が著しく低く、大冷害の年となってしまった。 稲作における冷害には、遅延型冷害、障害型冷害の2種類があるのだが、今年 の冷害は幼穂形成期、すなわち花粉などが成熟していく時期に低温条件が作用 し、授精能力のある花粉が形成阻害され、結果として不稔をもたらすタイプ、 障害型冷害の典型年である。 冷たい北東気流の影響をどの程度受けたかによって、冷害の程度にも地域差が 生まれるし、また作付けされた品種の耐冷性の度合によっても被害の程度は変 わってくる。 栽培上の管理から言えば、この低温に対して水田の水位をあげて、水温で幼穂 を守ってやる深水かんがいが有効な手だてとして知られている。 ところが、兼業農家では毎日の水位管理まで手が回らず、また、そうした管理 を呼び掛けるべき営農指導機関の対応も後手に回ってしまったという悪条件の 重なりあいが、戦後最悪とも言える冷害を招いてしまった。 食味のよい銘柄米に作付けが偏向してしまっている現状も、耐冷性の点から被 害を大きくしたとの指摘もなされている。 例によって、マスコミあるいは評論家たちは「これは天災ではなく、人災では なかったか」なんて論評を一斉に語り始めるのだが、その人災の張本人を農民 たちだけに押し付けてしまうところに評論の身勝手さがある。 確かに兼業では、十分な深水管理まで手が行き届かなかったかもしれない。 しかしながら、毎年、減反を食料管理制度維持のために押し付けられ、生産者 米価を据え置、もしくは引き下げられてきた農民、生産者米価算定にあっては、 せっかくの生産コスト低減の努力がそのまま米価引き下げの根拠にされてしま ったのでは、一体何のための努力だったのかという現実がある。 確かに労働生産性は、作業の機械化によってここ数十年の間に飛躍的に向上し たかもしれないし、余剰労働力が兼業というスタイルを可能にしてきた。 しかしながら、その機械化には例え年間稼動時間がわずかという機械であって も、巨額の投資を必要とせねばならなかったし、雑草と病害虫対策には農薬依 存が必須という栽培体系がつくられてきた。 しかも、コメは原則的に国によって価格管理された作物なのだから、収益をあ げるためには価格ランクの高い銘柄の作付け、そして多収という選択をどうし ても取らざるをえないわけだ。 さらに、6月から7月にかけての栽培管理指導が、本当に深水かんがいの励行 を呼び掛けていたのかどうか、こうした指導組織側の対応も検証されねばなら ないだろう。 ともあれ、世間一般では店頭にコメが並ばないという異常な事態が続出してい る。 確かに皆無作に近い産地もあったにせよ、比較的低温の影響を受けなかった地 域もあるわけで、新米の出まわり時期にコメ屋の店頭からコメが消えるという 事態は不思議としかいいようがない。 コメ不足が予想されるのは、来年の新米出まわり前の時期であって、今のコメ 不足とは収穫されたコメがどこかに滞っているとしか説明がつかないのだ。 政府は、冷害に乗じてコメの緊急輸入を決めたが、本当にどれだけの収穫があっ たのかを把握しきれているのかどうかも疑わしいではないか。 政府米は集まらない、ヤミ米はヤミ米業者に集まる、この原因が一体何なのか、 今年の冷害は戦後の食糧政策の矛盾をコメが消えるという形で露呈させたとみ るのが正しいのかもしれない。 食糧管理制度を支えてきたと思われていたJAまでもが、実は不正規流通をやっ ていたなんていうニュースも、末端の農民にとっては「一体、誰を信用すれば いいんだ」という気持ちにさせる。 コメが店頭から姿を消し始めると、今度は「早く、コメの輸入を」なんて声が 賑わしくなってくるのだが、外食店の裏に捨てられる残飯は本当に減っている のだろうか。 満腹が当たり前と思うから、「コメが足りなけりゃ、輸入しろ」なんて無責任 な事を言っていられるのではないだろうか。 空腹を味わってこそ、一粒のコメにありがたさを感じることができるのだし、 ここまで自給率を下げてしまったことに、事の深刻さを感じることができると 思うのだ。 世界的なコメの流通量は1,300万t、そのうちの200万tが緊急輸入に よって日本に買い付けられるわけだが、今年の異常気象は何も日本だけではな いのだ。 1,300万tのコメとは、それを必要とする国があってことなのだし、日本 の緊急輸入による国際価格の上昇と流通量の減少は、確実にそれらの国の経済 と胃袋を圧迫する。 生活費におけるコメへの支出割合が数%という日本にとっての価格上昇分は、 経済力に乏しいコメ輸入国にとっては計り知れない打撃となることを忘れては ならない。 コメが足りないのなら、半年くらいは代用食で我慢してみてはどうだろうか。 200万tといわれる不足分(果たして、本当にこれだけ足りないのかどうか も疑問なのだが)で飢饉が起こるとは到底考えられないし、日本の食糧自給率 は3割を切っている、すなわち7割以上はすでに国外依存なのだ。 減反政策(すなわち、水田つぶし)を続けてきて、価格抑制策を農民に強いて、 政府在庫が無くなったから輸入するという国家は、ますます傲慢な国という評 価しかもらえなくなってしまうのではなかろうか。 そんな折、このコメ不足で一儲けをたくらむ輩がいるとすれば、せっかく獲れ たコメにしみこんだ農民たちの汗があまりに空しいというものだ。 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
農産物、とりわけコメについての市場開放問題が注目を集めている。 ガット・ウルグアイラウンドの最終局面が間近ということもあるが、これほど の関心の高まりはやはり100年来の不作、そして自主流通米市場の値上がり に品不足、コメの緊急輸入という一連の動きが「頭」ではなく、「胃袋」で食 糧問題を考えさせるからだろう。 僕はコメ作り農家ではないが、ひとまず数少ない「専業農家」の末席にいるの で、手痛い不作に半ば開き直りながらも、食糧問題を人それぞれが「胃袋」で 考える機会の到来を喜ばしくも思っているわけだ。 農産物の問題がテレビなどの公開討論番組で扱われる機会も増えてきている。 自由化賛成、反対、画面に登場する顔ぶれは「またこの人、この話か」という かわりばえのなさだが、局面が「頭でものを言う」事態から「胃袋で考える」 事態に移って、転向よろしく立場を変える人が出てくるかと思い気やさにあら ず、「発言」で飯を食っている人はやはり一徹だと感心してしまう。 だが、国内農業バッシングの対象とされる側に身を置くものとしては、農産物 市場解放を唱える人たちの「地に足のつかない批判」を毎度のことながら歯が ゆく感じ、「私が世論です、私が消費者です」なんていう語り口にはうんざり してしまう。 と同時に、心情論で「農家の代弁者」として登場されるる全農、全中のおえら 方の頼りなさにも毎度のことながら、期待を裏切られてしまうのだが。 それぞれが思想信条にたっての主張を行うのだから、噛み合わせが悪いのは当 然なのだが、詭弁を鋭く指摘するだけの生活観がさっぱり出てこない。 これでは、生産者の大きなため息がそこかしこから聞こえてこようというもの だ。 農産物の市場解放容認派から必ず登場してくるのが、「補助金体質を排して、 国際競争力を高めて生産性をあげるべき、そのためには農産物の輸入自由化も 必要」という論調である。 つまり、もっと「農民同士を競わせて、やる気のない、生産性の低い農家を淘 汰して、規模拡大によって生産性をあげよ」という論法である。 「国際競争力なんてあてにはしていないけれども、どちらに転ぶにせよ、農産 物(食糧)が安く手に入りすればいい」というのが本音であろう。 「市場解放」といっても、体裁は「外圧」が装われてはいるが、実際に輸入を 手掛けるのは「民族商社資本」であり、長期的な商戦略でみれば「農産物」の 流通を扱うことはもっとも確実な利益につながる。 もちろん、そんな思惑はけっしてテレビ討論に顔を見せることはないし、「安 くて、安定的に食料を」なんていう庶民派ぶったコメンテーターが「消費者の ため」と熱弁をふるって、業界の利益を「消費ニーズ」にすりかえているよう に見えるのだが。 食料品支出の割合が生活費に占める割合などは口にしない、諸外国との値段の 直接比較にばかり目を向けて「私達は、こんな割高な生活(出費)を余儀なく されている」、これは「農産物を国境措置によって(農家を)甘やかしている からに違いない」という論法である。 さらに、農業バッシングで毎度お馴染みなのが「補助金で懐を肥やす農家」み たいなイメージ、農政が多額の農業補助を行っている割に、さっぱり農産物が 安くならない(国際価格との差が縮まらない)のは、税金の無駄使いだ」とい うやつである。 そこに「9・6・4(クロヨン)」、「10・5・3・1(トーゴーサンピン)」 なんていう税捕捉の不公平がひっぱり出されると、「坊主に憎けりゃ、袈裟ま で憎い」である。 折も折、消費税率の見直しがそれとなく漂い、「なんで高い国内農産物に血税 をくれてやるんだ」なんていう天引き納税者の憤懣のはけ口にもされかねない。 しかしながら、いつの世でも政(まつりごと)は不満のはけ口を巧妙に仕立て あげるのが常であったし、情報隔離と社会の分断こそが統治の常道とされてき た史実を見逃してはならない。 弱いものが執拗にいじめの対象とされたり、故意に「差別」を作り出しては衆 目を「まだ恵まれている」という安堵へと誘導する、孤立集団を生み出すこと によって多数への帰属が保身のための手形でもあるかのようにしむける、群れ る「日本人」の気質は幾世紀にも渡る「生かさず、殺さず」の農民・農村統治 と無関係ではあるまい。 その昔には、「民、百姓」の年貢が治世を支えていたわけだし、「禄をはむ」 の言葉通り「食糧(コメ)を制するものが世を制す」という世でもあった。 工業化社会を謳歌する今にあっても、「食糧を制するものは世界を制す」とい う根本原理はなんら色あせることはないのだが、表面上「自由貿易」を装って 食い気をあらわにしないところに先進国ならでわの陰湿さがある。 話を元に戻そう。 「競争原理をもっと働かせる」ことによって何が起こるだろうか。 確かに食糧管理制度が、事実上形骸化しているとはいえ、表向きにはコメ生産 者、そして農協、食糧庁が「計画生産」を行っているという構図があり、減反 に背く国内自由化要求の一部農民の造反劇が「競争原理の必要性」を訴えかけ ているようにも見える。 「自由競争ができれば、安いコメづくりができる」という訴えができるのは、 既存の兼業スタイルのコメ生産農家と比較して、という前置きでは正しいだろ うが、国内にあまねく「自由競争で生き残れる環境(土地条件)」が生まれる かどうか、これは「全国、どこででも安いコメづくりが可能か」ということで ある。 「圃場規模を大きくして大型機械投入による生産コストの低減を計り、安いコ メを提供する」、「自由競争」が何を自由に競わせるのかをはっきりさせない と、スケールメリットが直接、消費者価格の低減につながるかの期待を与えか ねない。 実際には規模拡大によるスケールメリットが発揮できそうな田畑そのものが、 どんどんと減ってきている、大規模な圃場を作り出せる土地条件は日本では限 られた地域にしか存在しないのである。 しかも、都市近郊の条件のよい田畑がどんどんと宅地化によって侵食されてい る、優良農地は優良宅地候補生なのだ。 宅地化、すなわち都市の肥大が近隣の農地価格を引き上げる、本来スケールメ リットが期待される農地ほど地代は高くなってしまい、これではいくら機械コ ストの低減がなされてもトータルコストは下がらない。 国内競争原理とは、結局のところ戦後農政が失敗した「専業農家の育成」を形 を変えて行い(農業の企業化、法人化の促進)、兼業農家から専業農家への農 地集積移行を進めるところに本質があるのではなかろうか。 その延長上に、商社資本の本格的参入が控えていることは農地法改正の動向を 見れば明らかだ。 家族農業から法人農業へ、現行の農地法による歯止めがはずされる下地は、家 族農業の困窮と後継者難という外堀から着々と埋められようとしている。 日本の国土を見つめれば、いかにスケールメリットを語ろうとも世界の農産物 輸出国との格差は埋めようがない、また、埋める方向で農業を語ろうとすると ころに大きな落とし穴があるのだ。 現実には、「競争原理」は農産物の産地化にあっては、「産地間競争」として 日常茶飯事に繰り広げられている光景なのだ。 その恩恵を誰が一番享受しているのか、「競争原理を国内農業に」なんて間の 抜けた話をしている人には、恩恵の「お」の字も授かっていないということだ ろうか。 競争原理がなにをもたらしているのか、例えば産地指定を受けるために特定作 物が過作を余儀なくされ、土壌病害の蔓延を防止するために農薬の多用がなさ れる事態を引き起こしているし、最悪の場合、土壌病害の多発によって産地の 看板を降ろすということもある。 生産者は安定供給の名のもとに(週休二日、労働時間短縮の報を横目に)、天 候のきまぐれや価格低迷、そして過重労働にもめげずに「ひたすら、働く」。 農薬と機械のために大幅に労働時間が減ったコメだからこそ、「兼業」スタイ ルが可能になったわけで、逆に兼業収入があるからこそ「兼業」は生き残って きたともいえる、その兼業農家が7割占めているのが今の日本の稲作なのだ。 農産物の市場解放によって「国内農業の生産性が高まる」、仮に高まったとし て、それではその恩恵は農民にももたらされるのか、「消費者の代弁者」を演 ずる評論家たちは、「農民の利益」にはまったく触れようとしないのは何故だ ろうか。 生産コストの低減が「安いコメづくり」をもたらすにせよ、それで農民の収入 が安定的に、しかも再生産意欲がわくものとなるような視点は口にされない。 「消費者の利益」一辺倒で、その下に横たわる農地の条件、流通事情、資材等 のコストファクター、そして生産者にとっても安全な生産環境、単に価格を比 較するだけでは農業問題は決して解決しない。 農産物が海外との価格比較でまな板に上がるなら、そこでは為替レートの変動 も問題とされねばならないし、なにより大切な事は価格とは商品の値打ちを買 い手がどう判断するのか、いかに価値を見出すのかで論ずべきものということ だ。 地に足をつけた見方をすれば、農産物を輸出することは農業の成立要素である 「土」をどんどんと国外に持ち出していることに他ならないし、「持続可能型 農業」に関心が高まっている時代の趨勢にあって、農産物が資源ナショナリズ ムを語り始めたなら、農産物自給を「国際分業」に委ねてしまった国がいつま で「安価な食糧」を手にいれられるだろうか。 競いあって「安全で安心できる農産物」を提供するための「競争原理」なら話 も分かるが、「いかに中間マージンを我が手にするか」といった競争原理では、 かえって「危ない農産物」の氾濫を招きかねない。 ただでさえ加工食品という「味覚と見た目を欺く食べ物」が摂取量の半分の時 代、その上さらに農薬でコントロールされた農産物の増加すれば、「人生80 年、定年後のライフスタイル」なんて呑気な事を言っていられる場合ではない と思うのだが。 情報隔離と社会分断に対抗していくためには、現地発のニュースソースを自ら どれだけ手に入れられるかが鍵となる。 パトロンのついた評論家の放談にカウチポテトする暇があったなら、パソコン 通信などで「他人の親戚」づきあいのできる生産者、あるいは消費者を見つけ た方が何倍も世の中が見通せる。 それが「マスコミ」の時代からの脱却、すなわち「パソコミ」の時代を活かす 生活者の知恵ではなかろうか。 堀田誠嗣
 目次へ
目次へ
 ホームページへ
ホームページへ
食のエッセイ>「食料自給の選択」恋愛論 1993/12/14
ガットウルグアイラウンドの最終合意に向けて、日本のコメの関税化受入れ、 ミニマムアクセス導入のシナリオが着々と進行している。 「自由貿易の最大の恩恵にあずかってきた日本が、ラウンド合意を壊すわけに はいけない」、「農産物とて、自由貿易の例外とはなりえない」。 食料生産に自ら携わることのない国民の多くにとって、バブル崩壊の不況下で どれだけ「食料生産を自国でまかなう」ことの意義を考える余裕があるだろう か。 「自由貿易の世界秩序から、つまはじきにされたなら貿易黒字国日本の不景気 どころの話ではなくなる」、「GDP2%の農業のために他産業がつまはじき にされたのではたまらない」、どうやら国民の7割が「関税化受入れやむなし」 と判断するのは身近に農業が存在しない事の証しなのかもしれない。 新政権の仕掛け人でもある連合の山岸会長は、「せっかく誕生した連立政権が 壊れてしまっては何にもならない。ウルグアイラウンド合意案の受入れもやむ を得ない」と、暗に連立政権与党内の関税化受入れ反対派を牽制している。 なるほど、万年野党と言われ続けてきた党派がバブル崩壊と相次ぐ疑獄、脱税 事件に乗じて、保守分裂勢力との相乗り政権にたどり着いた。 これはヨットレースみたいなもので、いかに相手を牽制しながら風を掴む帆を 操るかというマッチレースとも言える。 「小異を捨てて大同につく」、さしづめ今回の国内農業の進路に多大な影響を 及ぼす国家選択は、農産物の超輸入国にあっての「食料自給」を小異として切 り捨てるものだ。 農業が政権存続の踏み絵にされ、しかも「国民の大多数はそれを支持している」 という構図はどこから生まれてきたものなのか。 敗戦からの経済復興、食料難の時代から飽食の時代といわれる今日まで、日本 は「地方」と「都市」という機能分担の比重を食料政策によってコントロール してきたとも言える。 工業が目覚ましい発展を遂げることができたのは、地方から労働力が都市に向 かって流れ出すことなしにはありえなかった訳だし、その方策として「規模拡 大の農業、省力化を可能にする生産体系、価格抑制」がとられた。 農民は、農業のスタイルを「農業構造改善事業」という政策によって転換させ られ、農民の互助組織として生まれた「農協」が巧みにその出先として組み込 まれていったのだ。 食料難に苦しんだ時代から、食料自給率が3割を割り込むまでの時間、そして 農産物の貿易自由化への道を許容し、コメもその例外としないという「民意」 が作り出されるまでに、農民は何をしてこなければならなかったのか。 糞尿魚粕とわずかばかりの化学肥料(単肥)による農業スタイルから、多肥と 農薬と農業機械の3点セット農業への転換、この転換期に従来の農村は過疎化 と若年労働力の流出の洗礼を受けた。 化学肥料の多用に耐え、しかも機械収穫に適した品種育成に国費が投じられ、 単位面積あたり収量は増加した。 その間、農民は「生産性のアップとコスト低減」という暗示に導かれ、規模拡 大がそのゴールであるという「ささやき」になびいてきた。 しかも、「回りの生産者は市場の敵(かたき)」という市場至上主義しか見え てこない状況に囲いこまれ、収入を増やすために「たくさん獲ること、買って もらえるものを作ること」に腐心してきた。 生産性をあげるために機械化が進み、端境期の市場めがけて施設農業が広がり、 除草剤、殺虫剤、殺菌剤が「美人農産物」をつくりあげた。 恋人には「美人」、伴侶なら「器量よし」、残念ながら今の農家は消費者の恋 人に血道をあげてはいるが、その一方で消費者の方も伴侶を求めようとはしな いお気楽のシングルライフを楽しんでいる。 戦後農業は、ひたすら生産性と美人路線を走らされながら、生産性向上の相当 分を「農産物価格抑制策」によって相殺され、価格の単純比較で内外価格差の そしりに甘んじ、ついには農産物市場解放容認という「失恋」の結末を迎えて しまった。 実らぬ恋の原因は、単に相手が浮気者だったからだろうか、それとも結婚する 気もない相手に厚化粧で媚を売ったからだろうか、いづれにせよ、都市生活者 のほとんどは降りしきる雨に打たれながら待ちつづけていた農民に傘をさそう とはしなかった。 手取り足取りの「近代農業」という教科書は、恋の結末までは教えてくれなかっ たということだろうか。 失恋の痛手を負った農民は何を学んだのだろう。 「こうすれば相手に気に入られる、こうすれば美しくなれる、こうすればスマー トになれる。だから恋敵に負けないようにダイエットをし、この化粧品、この 機械を使いなさい」 言われるままにダイエットに励み、化粧をし、機械を買ってはみたものの、恋 人になるというよりも誰からもきれいに見られたいという思いがつのり、やが て恋の目的を見失ってしまった農民。 食料難の時代に求められた「生産性の向上」と食料自給率3割の時代の「生産 性の向上」とは、まったく意味が違うのである。 せっせと工業社会へ労働力を吐き出してきた農業、農村は、消費こそ美徳とも てはやされ始めた時点で、その違いに気付いて「我に返る」べきだった。 「万人への食料供給」こそが農業の本分と自分に言い聞かせ、教科書の教える ままに恋愛競争のサバイバルに身を投じていったわけだ。 ノウハウに長けた「恋の指南」に躍らされた農民が気付かなかったのは、当た り前のような「愛する心」じゃなかったろうか。 「恋人を得たい」ばかりに、「人を愛する」ことができなくなってしまったの じゃなかろうか。 失恋の腹癒せに相手の無理解を罵る前に、「私は本当に相手を愛していたのだ ろうか」、失恋は反面教師でもあるはずなのだ。 生産性の向上とともに何故「食料自給率の低下」が起こってきたのか。 それでも農民たちは「万人のために食料を提供する」という大儀にしがみつき、 一方で産地間競争に明け暮れてきた。 そんな中から「生産性の向上は規模拡大から」という神話が生まれ、飽食の時 代に懸命に化石燃料を食い散らかし、恋する人に毒を食わせるが如く農薬美人 の農作物増収に傾注してしまったのだ。 これこそが、工業社会にあっての農業の姿にほかならない。 今の農業に必要なのは美しく見せることではなく、愛し愛されることだ。 国民の7割が「コメの部分関税化やむなし」という選択をしたなら、残り3割 の人たちのために全身全霊を傾けてのパートナーシップに徹する、恋人と伴侶 はどこが違うのかを噛みしめる時ではないだろうか。 恋人になる努力を愛する努力に変える、これも失恋からの教訓なのだ。 それが分かった時、きっと「食料自給」を振った人たちはやがて自分達に見る 目がなかったことを後悔するに違いない。 悔しがらせるような脱皮ができるかどうか、農民よ、消費者よ、真のパートナー を探せ! 堀田誠嗣
© Seiji Hotta
 目次へ
目次へ
|