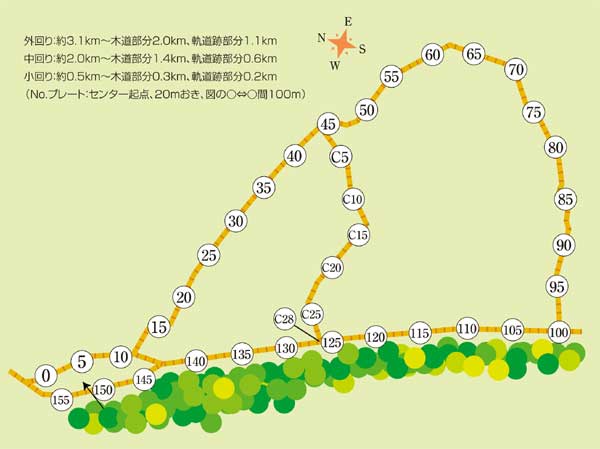
散策道を歩いたビジターが、センター情報板に記入したものです。
(センター職員の情報も含む)
温根内木道自然情報 184
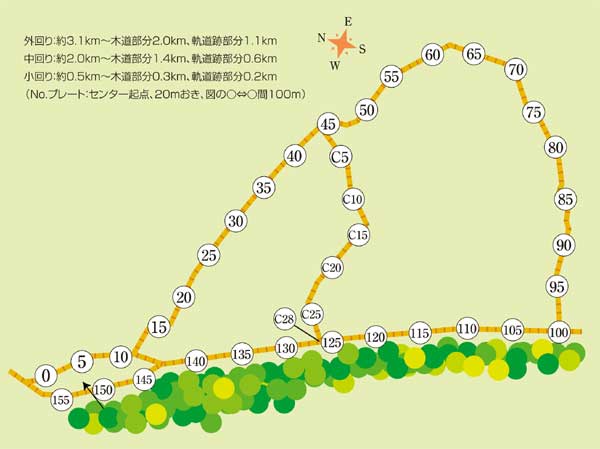
| A:シモ(10/13)〜何にどういう状態で霜が着いていたか気にかかります。位置的にヤチマナコ周辺、水温と気温の差で生まれた水蒸気が周りのヨ シなどに付着して霜を形成したのでしょう。空気中の水分が凍り、様々な花を着ける冬ももうすぐ、早朝散歩で霜の花を探してはどうでしょう。 B:ヘビ(9/20)〜10月に入っても暖かい日には出てくることもあります。いい冬眠場所を見つけられるといいですね。 C:ヒメキマダラヒカゲ(9/24)〜ヒカゲチョウの仲間(ジャノメチョウ科)で、サトキマダラヒカゲやヤマキマダラヒカゲなどそっ くりさんもたくさん翔んでいますが、少し小型。幼虫で越冬する。ただ食草がササ類なので高層湿原での目撃は珍しい。違う種かも? D:トガリネズミ死体(10/7)〜毎月のように木道上に、なぜでしょうね。 E:ゴキヅルだらけ(9/30)〜年々勢力を拡張しています。変わった実をつけるの ので、「あれは何ですか?」の問いも多い。お椀を二つ合わせたような形から「合器蔓」、中にはゴキブ リのような種子が2つ入っている。 ? F:山ぶどうをがんばってとったよ(10/7)〜今年は「たわわ」、 野鳥やリス、テンなどのために味わう程度で・・・ G:かえる発見(10/7)〜道を横断します。踏みつけないように・・・エゾアカガエル。 H:あかとんぼの交尾(9/20)〜まだ翔んでいます。アキアカネかな? ミヤマアカネかな? それとも・・・(先月号参照) I:エゾシマリス(9/20・23、10/7・14)〜もう早い個体では冬籠りしているかもしれません。。シマリスの冬籠りは、春の交尾を いかにうまく行なうかという子孫を残す戦略の中で、成獣メス-成獣オス-若メス-若オスの順とほぼ決まっています。まだ出会う機会はありますよ。 J:キリギリス、キリギリスにかこまれた(9/30、10/6)〜木道上でみかけるほとんどはハネナガキリギリス、 たまに草地でコオロギと間違えられるイブキヒメギスやヒメクサキリなど。囲まれたという状況は・・・ちょっと想像できない・・・「かまれた」でした。 K:モモンガ(10/7)〜8月にも目撃例が、しかし自身未確認。 L:バッタ野原・大きいバッタがみつかった(10/13)〜トノサマバッタかな? 他:チョウセンゴミシとコウライテンナンショウ(?)、ヒメカイウ〜共通点は何? 目立つ真っ赤な実をつけているくらいだが、空中:地上:水上とそれぞれ場所は 違うが点々と秋を語る。 日本に自生するのに朝鮮とか高麗が名に入るのは何故?と思わせる。チョウセンゴミシは滋養 強壮の生薬として有名、5つの味がすることから五味子と名が付いた。先に輸入生薬チョウセ ンゴミシとして珍重していたが、後に日本に自生するとわかっても、そのままの名としたとい う話も。漢方薬としての価値を高めようとしてチョウセンを残したわけではない、と思いたい。 コウライテンナンショウは和名ではマムシグサ、実に目を奪われないで茎(偽茎)をみるとその訳が解る。 ヒメカイウだけは湿原の内、水の上に倒れ込んでいる。もうミズバショウと間違われることはない。 |
| タンチョウ(a:10/14上空1羽)〜目撃が少なくなっている。センターで声を聞くことはしばしばだが、 なかなか姿が見えない。給餌場にまだ集まっていないので鶴居村の農道をウロウロすると目撃できる可能性大。タンチョウ目 的の方は、12月以降がベスト。日本のタンチョウは渡り鳥ではありません。念の為。 =渡り鳥:繁殖地と越冬地間を毎年決まった季節に移動する鳥。日本では春に繁 殖のため南から渡って秋に去る鳥を夏鳥、秋に渡来し春に去る鳥を冬鳥、旅の途中 に通過する鳥を旅鳥としている。他に何かしらの理由で渡りの途中などにたまに迷 い込む迷鳥もいる。一般にこれらを渡り鳥という。 渡り鳥以外では、その地方の中で繁殖地と越冬地を季節で別にする(山から里へなど)する鳥を漂鳥、一年中その地で見られるお馴染みの鳥を留鳥という。 ただ、毎年大部分は去るが一部は残りそのまま夏に繁殖する冬鳥や一部が南に去らずに越冬する夏鳥、一部が一年中里に居座る漂鳥(とされている鳥)等もいて、 同一種を全国またはその地域でみな同じ括りにできるとは限らないし、これらの分け方について異なった考えもある。 北海道では、本州以南で繁殖・越冬するが北海道には繁殖のため春に来て秋に去る鳥(ウグイス等)や、本州では旅鳥でも北海道で繁殖する鳥(ノゴマ等)は夏鳥 というなど本州とは事情が違うものも多いし、道東・道南で違うこともある。これからは気候変動の影響で「あれ!」ということが頻繁に起こるかもしれない。 長い距離を移動する渡り鳥は、年々環境が悪化しているなか、年2回(一回は幼鳥連れ)も大冒険をしている。彼等の通る道を確保しておいてほしいものである。 日本のタンチョウは、釧路湿原で繁殖・越冬をする留鳥といえる。ただ、数が増えたため釧路湿原だけでは営巣地を確保できず、新天地を求めたカップ ルが根室・十勝管内など道東の湿地や、遠く稚内近くのサロベツ原野や道央の勇払原野まで行って繁殖している。これらの多くは鶴居村や釧路市阿寒町を越冬地とし ているので「渡り鳥化」しているともいえる。冬に決まった地に集まるのは、ねぐらとなる凍らない河川や餌の確保できる場所があるからだが、あたらしいカップル を誕生させる集団見合いの場としても必要不可欠、釧路湿原を大事にしたいものである。 ちなみに日本のツルの仲間は7種で、タンチョウ以外は冬鳥(マナヅルとナベヅル以外の来日は稀)。 アカゲラ(b:10/7)〜留鳥。年中毎日のようにお目にかかっている。センターの壁をコツコツ、我が家の壁もコツコツ。 他:シジュウカラ、ハシブトガラ、ゴジュウカラ、シマエナガ、コゲラは見つけや すい。オオアカゲラ、コアカゲラは運次第(生息個体数の違い)。シメ、ヒヨドリ が時たま。 |