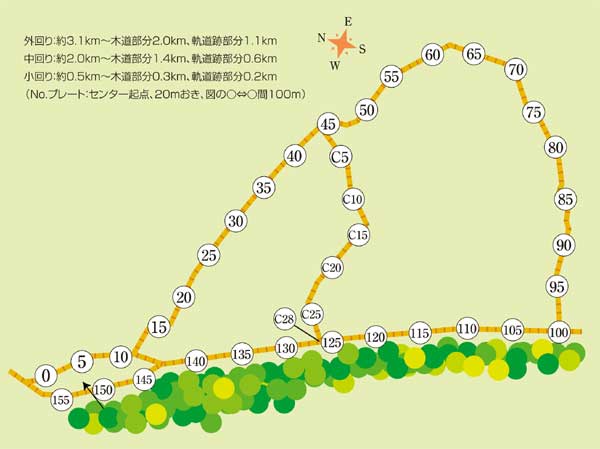
散策道を歩いたビジターが、センター情報板に記入したものです。
(センター職員の情報も含む)
温根内木道自然情報 170
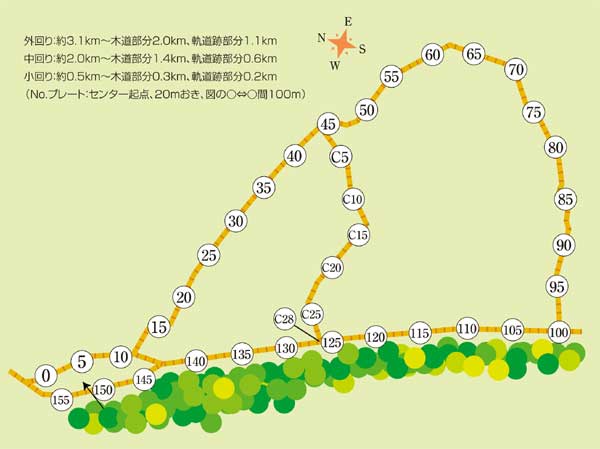
| A:エゾシマリス(7/15〜8/14多数)〜高層湿原での目撃例は初めて、個体数が増えて いるとは思えないが活動範囲は広がっている。伝言板は子供が記入したシマリスだらけ。 B:ミヤマカラスアゲハ(8/8)チョウ(菫色)(8/12)〜夏はチョウ の活動が活発な時期、いろんなチョウが舞っていたり、花にとまっていたりしています。伝言板に記入する際は、 名前がわからなくとも大きさや特徴をきちんと書いて下さい。色は案外、個人によって感覚が違います。一番い いのは、記憶のあるうちにセンターで図鑑をみたり質問をするなど、すぐに確認することです。 チョウと花との組み合わせも楽しもう!クジャクチョウと咲き始めたハンゴンソウ? C:ホザキシモツケ満開(7/18)〜丘陵地に近い湿地で、灌木林を作る樹木で、ピン クの華やかさは夏そのもの。準絶滅危惧種。 D:タチギボウシ(8/1)〜ハンノキ林の中や高層湿原に多く見られます。 ?E:エゾイヌゴマ(8/1)〜スゲ原にたくさん。茎を触ってみましょう。 F:ヘビ発見、黒いヘビ、シマヘビ、アオダイショウなど(7/17〜 8/11多数)〜湿原域のヘビはまずシマヘビ、アオダイショウは樹上性なので木道上での確かな発見例はありません。黒 いのはシマヘビの黒化型。 G:サワギキョウ/サワギキョウとドクゼリ・トウヌマゼリの群 落(8/1・13)〜白と紫のコントラスは夏から初秋にかけてのスゲ原を代表する景観。 ? ドクゼリ(畑?) H:クロバナロウゲ(7/18) I:エゾイトトンボ(8/10)でかい青とんぼ(8/4)〜スゲ原を覗くと何種かのイトトンボ(カラカネイトトンボ、キタ イトトンボなど)がミツガシワの葉などの上をノンビリ移動したり、交尾の姿勢のまま水面を求めている様などが見られる。「でかい青とんぼ」はルリボシヤン マのことかな? エゾトンボなど中型のものも多く翔ぶ。湿原はトンボの国でもある。釧路湿原では50種ほど確認されている。 雲や水やかさりと蜻蛉触れ合ひし 荒木正隆 ② J:エゾユキウサギ(8/8・12)〜この時期の目撃例は非常に珍しい。目撃した翌日に伝言板に記入したと思われますが、一件はセンター 裏手の林で時間帯不明、一件は木道上でホタル見学の途中?で夕方、どちらもさぞ驚いたでしょうね。ホタル以外でも「ナイトウォ〜ク」にどうぞ! K:ホタル(8/12)〜今年の8月は蒸し暑い日が続き、発生期間も長かったようです。今年のホタルの観察会「ホタルウィーク」は7月26日から 30日まで実施、513人もの参加者が「ほのかな光」のいろいろを学び楽しみました。 L:トキソウ(7/18・25、8/1〜終わりかけ)=先月号参照〜高層湿 原の夏は終わり、もう秋に入りました。 M:モウセンゴケ(8/1・6)〜この花目的のビジターの何人かは、「見 つからなかった」と寂しげでしたが、よく探すと見つけられたはず、そのくらい小さな花 です。見つけ出すポイントは、ミズゴケ丘塊の凹凸の境目あたり、虫を捕らえる葉をまず 探すこと。来年は頑張って下さい。 N:オオウバユリ終わりかけ(8/1) O:ツリフネソウ(8/1)〜やや湿ったところに、乾いた所にはキツリ フネ、並んでいる個所もある。 P:オニノヤガラ(7/26)〜この辺では数少ないラン科の花、葉はな く、まっすぐ伸びた茎の上部に壺型の花をたくさん着ける。 Q:キツリフネ(8/1)〜ツリフネソウと花の出方が少し違います。? |
| (a:7/18)コヨシキリの声〜盛んに鳴く時期は過ぎているはずだが・・、ヨシ原でしばし佇もう。 (b:7/18〜8/12多数)タンチョウ〜大きく分けて3ポイントで1羽から3羽の情報。中央テラスから 堤防道路を望むヨシ原では上空の飛翔、高層湿原と木道出口近辺のヨシ原では採餌の様子をじっくり。 (c:8/12)アカゲラ (d:8/1)ニュウナイスズメ (e:7/18・8/8)ウグイス (f:8/1)ショウドウツバメ〜湿原道路の阿寒川を横切る橋の両岸に大規模な営巣地がありましたが、護岸工事で消えてしまいました。野鳥 営巣地での工事はちょっとした工夫や工期の変更で、野鳥への被害を最小限に防げるものです。より営巣地の確保が困難な大型の鳥に目を向かいがちですが、東南ア ジアやオーストラリアなどから遠々と繁殖のために旅してくるわけですから、こちらが彼等の故郷といえます。故郷を大事にしたいものです。 (g:7/18)ノビタキ (h:7/22・8/11)ノゴマ・ベニマシコ 他:ハンノキ林の上を移動したりセンターのアンテナにとまるキジバト、木道脇から飛び出すアオジ、カラ類と混群で移動しているセンダイムシクイ、ヨシにとまるオオジュリンやシマセンニュウ等々、木道で遊ぶ?飛翔訓練中のヨシ原で巣立ったばかりの夏鳥たち。 ◎夏恒例のイベント「トンボ・ザリガニウォッチング」を7月23日(日)に、センターから5分ほどの釧路川右岸堤防沿いで行ないました。センターでトンボの見分け方の基本やザリガニについて−特に外来生物法の指定生物にウチダザリガニが加えられ、飼育に規制がかかったことで、釣ったザリガニを持ち帰ることが出来なくなったこと−などの説明の後、釣りざおやタモを担いで現場に向かいました。当日は気温が低く曇り空、トンボの飛翔がほとんど見られず、やむなくザリガニ釣りに専念することに。水中からエゾイヌゴマが出る温根内川の分流にづらっと竿を並べた甲斐もあって、参加19名(年齢一桁3名含む)で釣果160超、雌雄の違いなどを実物を掴みながら学びました。 |